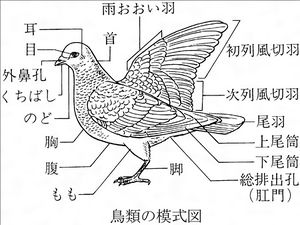ja>Motoriyo |
|
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) |
| 1行目: |
1行目: |
| − | {{Redirect|鳥}}
| + | [[ファイル:鳥類の模式図.jpg|サムネイル]] |
| | {{生物分類表 | | {{生物分類表 |
| | |名称 = 鳥綱 {{sname|Aves}} | | |名称 = 鳥綱 {{sname|Aves}} |
| | |fossil_range = 後期[[ジュラ紀]]–[[現世]]、{{Fossil range|150|0}} | | |fossil_range = 後期[[ジュラ紀]]–[[現世]]、{{Fossil range|150|0}} |
| | |色 = 動物界 | | |色 = 動物界 |
| − | |画像 = [[ファイル:Bird Diversity 2011.png|300px]] | + | |画像 = |
| − | |画像キャプション = 現存している鳥類およそ30の分類目のうち、<br />代表的な18種を示す。(クリックして拡大)
| |
| | |界 = [[動物|動物界]] {{sname||Animalia}} | | |界 = [[動物|動物界]] {{sname||Animalia}} |
| | |門 = [[脊索動物|脊索動物門]] {{sname||Chordata}} | | |門 = [[脊索動物|脊索動物門]] {{sname||Chordata}} |
| 11行目: |
10行目: |
| | |上綱 = [[四肢動物|四肢動物上綱]] {{sname||Tetrapoda}} | | |上綱 = [[四肢動物|四肢動物上綱]] {{sname||Tetrapoda}} |
| | |綱 = '''鳥綱''' {{sname||Aves}} | | |綱 = '''鳥綱''' {{sname||Aves}} |
| − | |学名 = [[w:Aves|Aves]]<br />{{AUY|Linnaeus|1758}}<ref>{{cite web |date=2014-01-26 |url= http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=80129&tree=0.1 |title=Systema Naturae 2000 / Classification, Taxon: Class Aves |work=Project: The Taxonomicon |publisher=Universal Taxonomic Services |accessdate=2014-06-21}}</ref> | + | |学名 = [[Aves]]<br />{{AUY|Linnaeus|1758}}<ref>{{cite web |date=2014-01-26 |url= http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=80129&tree=0.1 |title=Systema Naturae 2000 / Classification, Taxon: Class Aves |work=Project: The Taxonomicon |publisher=Universal Taxonomic Services |accessdate=2014-06-21}}</ref> |
| | |和名 = 「鳥(とり)」 | | |和名 = 「鳥(とり)」 |
| − | |英名 ="[[w:Bird|Bird]]" | + | |英名 ="[[Bird]]" |
| | |下位分類名 = 亜綱 | | |下位分類名 = 亜綱 |
| | |下位分類 = | | |下位分類 = |
| 19行目: |
18行目: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | '''鳥類'''(ちょうるい)とは、'''鳥綱'''(ちょうこう、'''Aves''')すなわち[[脊椎動物亜門]]([[脊椎動物]])の一[[綱 (分類学)|綱]]<ref name="iwabio">岩波生物学辞典 第4版、928頁。</ref><ref name="kojien5">広辞苑 第五版、1751頁。</ref>に属する[[動物]]群の総称。日常語で'''鳥'''(とり)と呼ばれる動物である。 | + | '''鳥類'''(ちょうるい)'''鳥綱'''(ちょうこう、'''Aves''') |
| | | | |
| − | 現生鳥類 ([[w:Modern birds|Modern birds]]) は[[くちばし]]を持つ[[卵生]]の脊椎動物であり、一般的には(つまり以下の項目は当てはまらない種や齢が現生する)体表が[[羽毛]]で覆われた[[恒温動物]]で、[[歯]]はなく、[[前肢]]が[[翼]]になって、[[飛翔]]のための[[適応]]が顕著であり、[[二足歩行]]を行う<ref name=Dic_Ornithology_552-553>[[#鳥類学辞典|『鳥類学辞典』 (2004)]]、552-553頁</ref>。
| + | 脊椎動物門の鳥綱に分類される動物の総称。体は流線形で,[[羽毛]]に覆われる。 |
| | | | |
| − | == 概説 ==
| + | 口器は[[嘴]]になり,前肢は[[翼]]に変形しており,飛翔力は多くが備えているが,[[ダチョウ]]や[[ペンギン]]類など失った鳥もいる。 |
| − | {{仮リンク|現存分類群|en|Extant taxon|label=現存}}する鳥類は約1万種であり<ref name=IOC4.2>{{cite web |title=IOC World Bird List Version 4.2 |url=http://www.worldbirdnames.org/ |doi=10.14344/IOC.ML.4.2 |accessdate=2014-07-29}}</ref>(これまでの各分類に基づき、8,600種<ref name="iwabio" />や、9,000種<ref name="kojien5" />などとしているものもある)、[[四肢動物]]のなかでは最も種類の豊富な[[綱 (分類学)|綱]](分類目)となっている。現存している鳥類の大きさは[[マメハチドリ]]の5cmから[[ダチョウ]]の2.75mにおよび、体重はマメハチドリが2g<ref name=Yamagishi2002_36>[[#山岸2002|山岸 (2002)]]、36頁</ref>、ダチョウは100kgである<ref name=Gill_30>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、30頁</ref>。[[古生物学|化石記録]]によれば、鳥類は{{nowrap|1億5,000万}}年から{{nowrap|2億}}年前ごろの[[ジュラ紀]]の間に、[[獣脚類]][[恐竜]]から[[進化]]したことが示されている<ref name="AP-20140731">{{cite news |last=Borenstein |first=Seth |title=Study traces dinosaur evolution into early birds |url=http://apnews.excite.com/article/20140731/us-sci-shrinking-dinosaurs-a5c053f221.html |date=2014-07-31 |work=[[w:AP News|AP News]] |accessdate=2015-03-08}}</ref><ref name="SCI-20140731">{{cite journal |title=Sustained miniaturization and anatomical innovation in the dinosaurian ancestors of birds |url=http://www.sciencemag.org/content/345/6196/562 |date=1 August 2014 |journal=[[サイエンス|Science]] |volume=345 |issue=6196 |pages=562–566 |doi=10.1126/science.1252243 |accessdate=2 August 2014 |last1=Lee |first1=Michael S. Y. |first2=Andrea|last2=Cau |first3=Darren|last3=Naish|first4=Gareth J.|last4=Dyke}}</ref>。そして最も初期の鳥類として知られているのが、[[中生代]]ジュラ紀後期の[[始祖鳥]] (''Archaeopteryx'') で、およそ{{nowrap|1億5,000万}}年前である<ref name=Dic_Ornithology_1-2>[[#鳥類学辞典|『鳥類学辞典』 (2004)]]、1-2頁</ref>。現在では大部分の[[古生物学]]者が、鳥類を約{{nowrap|6,550万}}年前の[[K-T境界|K-T境界絶滅イベント]]を生き延びた、恐竜の唯一の[[系統群]]であると見なしている。
| |
| | | | |
| − | 現生鳥類の特徴は、羽毛があり、歯のない[[くちばし]]を持つこと、硬い殻を持つ卵を産むこと、高い[[代謝]]率、二心房二心室の[[心臓]]、そして軽量ながら強靭な[[骨格]]を持つことである<ref name=Dic_Ornithology_552-553 />。翼は前肢が進化したもので、ほとんどの鳥がこの翼を用いて飛ぶことができるが、[[平胸類]](走鳥類)や、[[ペンギン|ペンギン類]]、いくつかの島嶼に適応した[[固有種]]などでは翼が退化して飛べなくなっている。それでも現存する鳥類のすべての種が翼を持つが<ref name=Dic_Ornithology_552-553 />、数百年前に[[絶滅]]してしまった[[モア|モア類]]のように、完全に翼を失った例もある<ref name=Dic_Ornithology_805-806>[[#鳥類学辞典|『鳥類学辞典』 (2004)]]、805-806頁</ref>。また鳥類は飛翔することに高度に適応した、独特な[[消化器]]や[[呼吸器]]を持っている。ある種の鳥類、とりわけ[[カラス科|カラス類]]や[[オウム目|オウム類]]は最も知能の高い動物種のひとつであり、多くの種において{{仮リンク|動物の道具使用|en|Tool use by animals|label=道具を加工して使用}}することが観察されており、また、さまざまな社会的な種が、世代間の知識の文化的伝達<!--事例を示すべき-->を示している。
| + | [[定温動物]]で[[卵生]]のほか,骨格,内臓などに,飛行に有利な軽量化や[[代謝]]のための著しい[[適応]]が見られる。こうした特徴は約 6500万年前に絶滅したとされる[[恐竜]]も共有しているものがおり,鳥類は絶滅期を生き残った恐竜の系統であると考えられるようになった。 |
| − | | |
| − | 鳥類は[[北極]]から[[南極]]に至る[[地球]]上の広範囲の[[生態系]]に生息している。また、多くの種が毎年長距離の[[渡り]]を行い、さらに多くが不規則な短距離の移動を行っている。
| |
| − | | |
| − | 鳥類は{{仮リンク|社会的行動|en|social behavior| label=社会的}}であり、視覚的な信号や、地鳴き (call)、さえずり ([[w:Bird vocalization|song]]) などの聴覚的な伝達行動を取り、そして{{仮リンク|巣のヘルパー|en|Helpers at the nest|label=協同繁殖}}や捕食(狩り)行動、群れ形成 ([[w:Flocking (behavior)|flocking]])、モビング([[w:Mobbing (animal behavior)|mobbing]]、偽攻撃、捕食者に対して群れをなして騒ぎ撃退する行動)などの社会的行動に加わる<ref name=Dic_Ornithology_330・798-799>[[#鳥類学辞典|『鳥類学辞典』 (2004)]]、330頁、798-799頁</ref>。大多数の種は社会的に[[一夫一婦制|一夫一婦]]であり、この関係は通常1回の繁殖期ごととなる。なかには数年にわたるのもあるが、生涯続くものは稀である。[[一夫多妻制|一夫多妻]](複数の雌)や、稀に[[一妻多夫制|一妻多夫]](複数の雄)の繁殖システムを持つ種も存在する。卵は通常、巣に産卵され、親鳥によって{{仮リンク|抱卵|en|Egg incubation}}される。ほとんどの鳥類は孵化後、しばらく続けて親鳥が雛(ひな)の世話をする。
| |
| − | | |
| − | 多くの種が経済的重要性を担っており、ほとんどは[[狩猟]]対象もしくは[[家禽]]であるが、なかには[[ペット]]として、とりわけ[[スズメ亜目|鳴禽類]]や[[オウム目|オウム類]]のように人気のある種もある。それ以外にも、[[グアノ]](鳥糞石)が[[肥料]]にするために採取される。鳥類は、[[宗教]]から[[ポピュラー音楽]]の歌詞にいたるまで、人間のあらゆる文化面によく登場する。しかし、分かっているだけで約130種の鳥が、17世紀以降の人間の活動によって絶滅し<ref name=Gill_626>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、626頁</ref><ref name=Yamashina2006_16>[[#山階2006|山階鳥研 (2006)]]、16頁</ref>、さらにそれ以前には数百種以上が絶滅している。保全への取り組みが進められてはいるが、現在約1,200種の鳥が、人的活動によって絶滅の危機に瀕している。
| |
| − | | |
| − | == 進化と分類学 ==
| |
| − | {{main|{{仮リンク|鳥類の進化|en|Evolution of birds}}}}
| |
| − | [[ファイル:Naturkundemuseum Berlin - Archaeopteryx - Eichstätt.jpg|alt= Slab of stone with fossil bones and feather impressions|thumb|right|[[始祖鳥]] (''Archaeopteryx'')。既知の最古の鳥類。]]
| |
| − | | |
| − | 最初の体系的な鳥類の[[分類]]は、1676年の書物、『鳥類学』 ''Ornithologiae'' において[[フランシス・ウィラビイ]]と[[ジョン・レイ (博物学者)|ジョン・レイ]]によって編み出された<ref name=Gill_77>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、77頁</ref><ref>{{Cite book |last=del Hoyo |first=Josep |coauthors=Andy Elliott and Jordi Sargatal |title=[[w:Handbook of Birds of the World|Handbook of Birds of the World]], Volume 1: Ostrich to Ducks |year=1992 |publisher=[[w:Lynx Edicions]] |location=Barcelona |isbn=84-87334-10-5}}</ref>。[[カール・フォン・リンネ]]は1758年に、この成果をもとに現在使用されている[[分類学|分類体系]]を考案した<ref>{{la icon}} {{Cite book |last=Linnaeus |first=Carolus |authorlink=w:Carolus Linnaeus |title=[[w:Systema Naturae|Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata]] |publisher=Holmiae. (Laurentii Salvii) |year=1758 |page=824 |url=}}</ref>。鳥類は、{{仮リンク|リンネ式分類|en|Linnaean taxonomy}}では生物学的分類目の鳥[[綱 (分類学)|綱]] (class Aves) に分類される。{{仮リンク|系統命名学|en|Phylogenetic nomenclature|label=系統分類}}では鳥綱を恐竜である[[獣脚類]]の[[系統群]]に分類している<ref name="Theropoda">{{Cite journal |date=2007-01 |title=Higher-order phylogeny of modern birds (Theropoda, Aves: Neornithes) based on comparative anatomy. II. Analysis and discussion | journal=[[w:Zoological Journal of the Linnean Society|Zoological Journal of the Linnean Society]] |volume=149 |issue=1 | pages=1–95 |doi=10.1111/j.1096-3642.2006.00293.x |pmid=18784798 |last1=Livezey |first1=Bradley C. |last2=Zusi |first2=RL |pmc=2517308}}</ref>。鳥類とその姉妹群である[[ワニ]][[系統群]]には、 [[主竜類]]系統群の代表として現存する[[爬虫類]]が唯一含まれる。[[系統学|系統学的]]には通常、鳥類は現生鳥類と始祖鳥 (''Archaeopteryx'') の[[最も近い共通祖先]] (MRCA) の子孫のすべてであると定義されている<ref>{{Cite book|last=Padian |first=Kevin |authorlink=w:Kevin Padian |author2=L.M. Chiappe Chiappe LM |editor=[[w:Philip J. Currie|Philip J. Currie]] and Kevin Padian (eds.) |title=Encyclopedia of Dinosaurs |year=1997 |publisher=[[w:Academic Press|Academic Press]] |location=San Diego |pages=41–96 |chapter=Bird Origins |isbn=0-12-226810-5}}</ref>。始祖鳥(1億5,000万年ごろのジュラ紀後期<ref name=Dic_Ornithology_1-2/>)は、この定義のもとで最も古い既知の鳥である。一方、[[ジャック・ゴーティエ]]やファイロコード ([[w:PhyloCode|PhyloCode]]) システムの支持者たちは、鳥綱を現生鳥類だけを含む[[クラウン生物群]]として定義している。これは、化石のみで知られるほとんどのグループを鳥綱(鳥類)から除外し、代わって、鳥類およびそれらを '''[[鳥群]]''' (Avialae、「鳥の仲間」<ref name=Dave_208-209>[[#恐竜学入門|『恐竜学入門』 (2015)]]、208-209頁</ref>)に位置づけることがなされている<ref>{{Cite book|last=Gauthier |first=Jacques|editor=Kevin Padian |title=The Origin of Birds and the Evolution of Flight|series= Memoirs of the California Academy of Science '''8'''|year=1986|pages=1–55|chapter=Saurischian Monophyly and the origin of birds|isbn=0-940228-14-9 |publisher=Published by California Academy of Sciences |location=San Francisco, CA}}</ref>。これはひとつには、伝統的に獣脚類恐竜と考えられている動物との関連における、始祖鳥の位置づけについての不確かさを回避するためである<!-- See WP:RS<ref>http://www.phylonames.org/forum/viewtopic.php?t=7</ref> --><!--Mayr et al. 2005 "A well-preserved Archaeopteryx specimen with theropod features" + comment + Mayr's comment on the comment-->。
| |
| − | | |
| − | すべての現生鳥類は'''新鳥亜綱'''に位置づけられており、ここには2つの下位分類が存在する。[[古顎類]] (Palaeognathae) は飛べない[[平胸類]](走鳥類、たとえばダチョウなど)とほとんど飛べない[[シギダチョウ科|シギダチョウ類]]からなり、広く多様化している[[新顎類]] (Neognathae) はこれ以外のすべての鳥類を含む。この2つの下位分類はよく上目として扱われるが<ref>{{cite web|url=http://people.eku.edu/ritchisong/birdbiogeography1.htm |last=Ritchison |first=Gary |title=Bird biogeography |accessdate=2014-06-22}}</ref> 、[[w:Bradley C. Livezey|Livezey]] や Zusi はこれを「[[コーホート]]」 ("Cohort") に位置づけている<ref name="Theropoda"/>。分類学的な観点により一様ではないが、現存している既知の鳥類の種数はおよそ9,700種以上<ref name=Gill_30 />、9,930種<ref>{{cite book |last=Clements |first=James F. |authorlink=w:James Clements |title=[[w:The Clements Checklist of Birds of the World|The Clements Checklist of Birds of the World]] |edition=6th |year=2007 |publisher=[[w:Cornell University Press|Cornell University Press]] |location=Ithaca, NY |isbn=978-0-8014-4501-9}}</ref>から10,530種<ref name=IOC4.2/>となる。
| |
| − | | |
| − | === 恐竜と鳥類の起源 ===
| |
| − | {{main|{{仮リンク|鳥類の起源|en|Origin of birds}}}}
| |
| − | [[ファイル:Confuciusornis_sanctus_(2).jpg|thumb|alt= 無数のひび割れと、対になった長い尾羽を含む、鳥の羽と骨の痕跡のある白い岩の板。|中国で発見された白亜紀の鳥、[[孔子鳥]] (''Confuciusornis'')。]]
| |
| − | 大部分の科学者が、化石と生物学的な証拠から、鳥類が特殊化された獣脚類恐竜の亜群であることを認めている<ref>{{Cite journal |last=Prum |first=Richard O. |title=Who's Your Daddy |journal=Science |volume=322 |pages=1799–1800 |year=2008 |month=December |doi=10.1126/science.1168808|pmid=19095929|issue=5909|issn=0036-8075}}</ref>。さらに具体的には、鳥類はそのなかでも[[マニラプトル類]]という、[[ドロマエオサウルス科|ドロマエオサウルス類]]や[[オヴィラプトル|オヴィラプトル類]]を含む[[獣脚類]]の仲間であるとする<ref name=Yamagishi2002_4-7>[[#山岸2002|山岸 (2002)]]、4-7頁</ref><ref>{{Cite book |last=Paul |first=Gregory S. |authorlink=w:Gregory S. Paul |chapter=Looking for the True Bird Ancestor |year=2002 |title=Dinosaurs of the Air: The Evolution and Loss of Flight in Dinosaurs and Birds |location=Baltimore |publisher=Johns Hopkins University Press |isbn=0-8018-6763-0 |pages=171–224}}</ref>。しかし、鳥類に関係の近い非鳥類型獣脚類の化石が発見されるたびに、それまで明瞭だった鳥類と非鳥類の区別が曖昧になっている<ref name=Dic_Ornithology_185>[[#鳥類学辞典|『鳥類学辞典』 (2004)]]、185頁</ref>。1990年代以降の中国東北部の[[遼寧省]]での発見では、多くの小形[[羽毛恐竜|獣脚類恐竜に羽毛があった]]ことが明らかになったが<ref name=Dave_217-220>[[#恐竜学入門|『恐竜学入門』 (2015)]]、217-220頁</ref>、それはこの曖昧さをさらに助長した<ref>{{Cite book |last=Norell |first=Mark |coauthors=Mick Ellison |year=2005 |title=Unearthing the Dragon: The Great Feathered Dinosaur Discovery |location=New York |publisher=Pi Press |isbn=0-13-186266-9 |pages=}}</ref>。それでも2014年には、研究者らにより獣脚類恐竜からの鳥類の進化の詳細が報告された<ref name="AP-20140731"/><ref name="SCI-20140731"/>。
| |
| − | | |
| − | 現代[[古生物学]]における一致した見解は、鳥類ないし[[鳥群]] ([[w:Avialae|Avialae]]) は、ドロマエオサウルス類、[[トロオドン科|トロオドン類]]を含む、デイノニコサウルス類 ([[w:Deinonychosauria|Deinonychosauria]]) の最も近縁であるとする<ref name=Xiaotingia>{{cite journal |title=An ''Archaeopteryx''-like theropod from China and the origin of Avialae |url=http://www.nature.com/nature/journal/v475/n7357/full/nature10288.html |date=28 July 2011 |journal=Nature |volume=475 |pages=465–470 |doi=10.1038/nature10288 |issue=7357 |author=Xing Xu, Hailu You, Kai Du and Fenglu Han |pmid=21796204}}</ref> 。さらに、これらは[[原鳥類]] ([[w:Paraves|Paraves]]) と呼ばれるグループを構成する。[[ドロマエオサウルス科]]の[[ミクロラプトル]](ミクロラプトル・グイ、''[[ミクロラプトル#M. gui|Microraptor gui]]'')<ref>{{Cite book|和書 |author=土谷健 |editor=小林快次監修 |year=2013 |title=そして恐竜は鳥になった |publisher=[[誠文堂新光社]] |isbn=978-4-416-11365-3 |pages=81-82}}</ref>など、このグループに属するいくつかの基系統群 ([[w:Basal (phylogenetics)|basal]]) は、滑空ないし飛行が可能であったかもしれない特徴を持っている。最も基系統であるデイノニコサウルス類は非常に小型であり、この証拠においては、原鳥類に属する祖先が、{{仮リンク|樹上性|en|Arboreal locomotion}}であったか、滑空することができたと考えられ、あるいはそのいずれでもあった可能性を提起している<ref name="AHTetal07">{{Cite journal |last=Turner |first=Alan H. |date=2007-09-07 |title=A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight |url=http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/317/5843/1378.pdf |format=PDF |journal=Science |volume=317 |pages=1378–1381 |doi=10.1126/science.1144066 |pmid=17823350 |month=September |issue=5843 |issn=0036-8075 |last2=Pol |first2=D |last3=Clarke |first3=JA |last4=Erickson |first4=GM |last5=Norell |first5=MA |accessdate=2014-06-22}}</ref><ref name="xuetal2003">{{Cite journal |last1=Xu |first1=Xing |last2=Zhou |first2=Zhonghe |last3=Wang |first3=Xiaolin |last4=Kuang |first4=Xuewen |last5=Zhang |first5=Fucheng |last6=Du |first6=Xiangke |year=2003 |month=January |title=Four-winged dinosaurs from China |journal=[[ネイチャー|Nature]]|volume=421 |issue=6921 |pages=335–340 |doi=10.1038/nature01342 |pmid=12540892 |issn=0028-0836}}</ref>。近年の研究では、初期の鳥類は、肉食であった始祖鳥や羽毛恐竜とは異なり、[[草食動物|草食]]であったことが示唆されている<ref>{{Cite web |date=2011-07-27 |url=http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/30969/title/On-the-Origin-of-Birds/ |title=On the Origin of Birds |publisher=[[w:The Scientist|TheScientist]] |accessdate=2014-06-21}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | [[ジュラ紀]]後期の始祖鳥は、最初に発見された[[ミッシングリンク]] (transitional fossils) のひとつとして有名であり、この化石は19世紀後期の[[進化論]]を支持する証拠となった<ref name=Dave_208>[[#恐竜学入門|『恐竜学入門』 (2015)]]、208頁</ref>。始祖鳥は、従来の爬虫類の特徴である、歯や、鉤爪のある指、そして長い[[トカゲ]]に似た[[尾]]のみならず、現生鳥類のそれと同様な[[風切羽]]を持つ翼の存在を、明瞭に示した最初の化石であった<ref name=Dave_207-209>[[#恐竜学入門|『恐竜学入門』 (2015)]]、207-209頁</ref>。始祖鳥は、現生鳥類の直接の祖先であるとは考えられていないが、おそらくは現生鳥類の真の祖先の近縁であった<ref name ="mayretal2007">{{Cite journal |doi=10.1111/j.1096-3642.2006.00245.x |last1=Mayr |first1=G. |last2=Phol |first2=B. |last3=Hartman |first3=S. |last4=Peters |first4=D.S. |year=2007 |title=The tenth skeletal specimen of ''Archaeopteryx'' |url= |journal=Zoological Journal of the Linnean Society |volume=149 |issue= |pages=97–116}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 異論と論争 ===
| |
| − | 鳥類の起源をめぐっては多くの論争が行われてきた。初期の意見の相違には、鳥類が恐竜あるいはより原始的な[[主竜類]]から進化したのかというものも存在する。恐竜陣営のなかにも、[[鳥盤類]]恐竜と[[獣脚類]]恐竜のいずれのほうが、より鳥類の祖先としてより近いかについて意見の相違があった<ref name="Heilmann1927">Heilmann, Gerhard (1927). ''The Origin of Birds''. New York: Dover Publications.</ref>。鳥盤類(鳥の骨盤を持つ)と現生鳥類は、骨盤の構造が共通であるが、鳥類は[[竜盤類]](トカゲの骨盤を持つ)恐竜が起源であると考えられている。したがってかれらの骨盤の構造は、互いに[[収斂進化|無関係に進化した]]ものである<ref>{{Cite journal |last=Rasskin-Gutman |first=Diego |month=March |year=2001 |title=Theoretical morphology of the Archosaur (Reptilia: Diapsida) pelvic girdle |journal=[[w:Paleobiology (journal)|Paleobiology]] |volume=27 |issue=1 |pages=59–78|doi=10.1666/0094-8373(2001)027<0059:TMOTAR>2.0.CO;2 |last2=Buscalioni |first2=Angela D.|issn=0094-8373}}</ref>。事実、鳥類のような骨盤の構造は、{{仮リンク|テリジノサウルス科|en|Therizinosauridae}}として知られる獣脚類の特異なグループの進化において、3度出現している。
| |
| − | | |
| − | [[ノースカロライナ大学]]の鳥類古生物学者[[アラン・フェドゥーシア]]のような一部の少数派の研究者は、主流派の意見に異議を唱えており、鳥類が恐竜から進化したのではなく、[[ロンギスクアマ]]のような初期の爬虫類から進化したと主張している<ref>{{Cite journal |last=Feduccia |first=Alan |month=November |year=2005|title=Do feathered dinosaurs exist? Testing the hypothesis on neontological and paleontological evidence |journal=Journal of Morphology |volume=266 |issue=2 |pages=125–66 |doi=10.1002/jmor.10382 |pmid=16217748 |issn=0362-2525 |last2=Lingham-Soliar |first2=T |last3=Hinchliffe |first3=JR}}</ref>(この学説にはほとんどの[[古生物学|古生物学者]]が反対している<ref>{{Cite journal |last=Prum |first=Richard O. |month=April |year=2003 |title=Are Current Critiques Of The Theropod Origin Of Birds Science? Rebuttal To Feduccia 2002 |journal=[[w:The Auk|The Auk]] |volume=120 |issue=2 |pages=550–61 |doi=10.1642/0004-8038(2003)120[0550:ACCOTT]2.0.CO;2 |jstor=4090212|issn=0004-8038}}</ref>)。
| |
| − | | |
| − | === 初期の鳥類の進化 ===
| |
| − | {{See also|化石鳥類の一覧}}
| |
| − | | |
| − | {{Cladogram
| |
| − | | cladogram = {{clade|style=font-size:80%
| |
| − | |label1=鳥綱
| |
| − | |1={{clade
| |
| − | |1=[[始祖鳥]]<br />''[[w:Archaeopteryx|Archaeopteryx]]''
| |
| − | |label2= [[w:Pygostylia|パイゴスティル類]]
| |
| − | |2={{clade
| |
| − | |1=[[孔子鳥]]<br />''[[w:Confuciusornis|Confuciusornis]]''
| |
| − | |label2= [[w:Ornithothoraces|鳥胸類]]
| |
| − | |2={{clade
| |
| − | |1=[[エナンティオルニス類]]<br />[[w:Enantiornithes|Enantiornithes]]
| |
| − | |label2= [[真鳥類]]
| |
| − | |2={{clade
| |
| − | |1=[[ヘスペロルニス類]]<br />[[w:Hesperornithiformes|Hesperornithiformes]]
| |
| − | |2=現生鳥類<br />[[w:Neornithes|Neornithes]]
| |
| − | }}
| |
| − | }}
| |
| − | }}
| |
| − | }}
| |
| − | }}
| |
| − | | caption = 簡略化した基礎鳥類 (Basal bird) の系統発生<br />キアッペ (Chiappe)、2007 に基づく<!--Basal bird phylogeny simplified after Chiappe, 2007--><ref name="chiappe2007">{{cite book|last=Chiappe |first=Luis M. |year=2007 |title=Glorified Dinosaurs: The Origin and Early Evolution of Birds |location=Sydney |publisher=University of New South Wales Press |isbn=978-0-86840-413-4}}</ref>
| |
| − | }}
| |
| − | | |
| − | 鳥類の広範な形態への多様化は、[[白亜紀]]の間に起こった<ref name="chiappe2007"/>。鉤爪のついた翼や歯といったような、[[共有派生形質]]を維持したままのグループも多く存在したが、歯は、現生鳥類(新顎類)を含むいくつものグループで、個々に失われていった。始祖鳥や{{仮リンク|ジェホロルニス|en|Jeholornis}}のような最も初期の形態では、かれらの祖先が持っていた、長く骨のある尾を保持していたが<ref name="chiappe2007"/>、一方でパイゴスティル類に属するより進化した鳥類の尾は、{{仮リンク|尾端骨|en|Pygostyle}}の出現により短くなった。およそ9,500万年前の後期白亜紀には、すべての現生鳥類の祖先は、より優れた嗅覚を進化させた<ref>{{cite web|url=http://www.cosmosmagazine.com/news/4223/birds-survived-dino-extinction-with-keen-senses |title=Birds survived dino extinction with keen senses |author=Agency France-Presse|date=2011-04-13 |publisher=Cosmos Magazine |accessdate=2014-06-22}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 最初の、大規模で多様化した短尾の鳥類の系統として進化したのが、[[エナンティオルニス類]]、あるいは別名「反鳥類」である。このように命名されたのは、かれらの肩甲骨の構造が、現生鳥類のそれと反転していることに由来している。エナンティオルニス類は生態系において、[[渉禽類|渉禽]](しょうきん)のように砂浜で餌をあさるものや、魚を捕食するものから、樹上に棲むもの、種子を食べるものまで、多彩な[[ニッチ|生態的地位]](Ecological niche、生存環境の範囲<ref name=Dic_Ornithology_439-440>[[#鳥類学辞典|『鳥類学辞典』 (2004)]]、439-440頁</ref>)を占有した<ref name="chiappe2007"/>。さらに進んだ系統では、魚を捕食することに適応した、一見[[カモメ亜科|カモメ類]]に似た[[イクチオルニス]]属がある<ref>{{Cite journal |last=Clarke |first=Julia A. |coauthors= |month=September |year=2004 |title=Morphology, Phylogenetic Taxonomy, and Systematics of ''Ichthyornis'' and ''Apatornis'' (Avialae: Ornithurae) |journal=Bulletin of the American Museum of Natural History |volume=286 |pages=1–179 |doi= 10.1206/0003-0090(2004)286<0001:MPTASO>2.0.CO;2|url=http://digitallibrary.amnh.org/dspace/bitstream/2246/454/1/B286.pdf|format=PDF|issn=0003-0090 |accessdate=2014-06-22}}</ref>。中生代の海鳥の目のひとつである{{仮リンク|ヘスペロルニス類|en|Hesperornithes|label=ヘスペロルニス目}}は、海洋環境における魚の捕食に非常によく適応して、飛翔する能力を失い、主として水中に生活するようになった<ref name="chiappe2007"/>。
| |
| − | | |
| − | === 現生鳥類の多様化 ===
| |
| − | {{See also|シブリー・アールキスト鳥類分類|{{仮リンク|恐竜の分類|en|dinosaur classification}}}}
| |
| − | すべての現生鳥類を含む系統である[[真鳥類|真鳥亜綱]]が、白亜紀の終わりまでにいくつかの現代の系統へと進化したことが、主に {{Snamei|en|Vegavis}} 属の発見によって現在わかっている<ref>{{Cite journal |last=Clarke |first=Julia A. |month=January |year=2005 |title=Definitive fossil evidence for the extant avian radiation in the Cretaceous |journal=Nature |volume=433 |issue=7023 |pages=305–308 |doi=10.1038/nature03150 |pmid=15662422 |url=http://www.digimorph.org/specimens/Vegavis_iaai/nature03150.pdf|format=PDF |last2=Tambussi |first2=CP |last3=Noriega |first3=JI |last4=Erickson |first4=GM |last5=Ketcham |first5=RA |accessdate=2014-06-23}} [http://www.nature.com/nature/journal/v433/n7023/suppinfo/nature03150.html Nature.com] - 概要</ref>。そして2つの上目、すなわち[[古顎類]]と[[新顎類]]に分岐した。古顎類には平胸類(走鳥類)とシギダチョウ類が含まれる。もう一方の新顎類からの基系統 (basal) の分岐が、上目としての[[キジカモ類]](キジカモ上目、Galloanserae)のグループであり、これには[[カモ目]]([[カモ|カモ類]]、[[雁|ガン類]]、[[ハクチョウ|ハクチョウ類]]、[[サケビドリ科|サケビドリ類]])と[[キジ目]]([[キジ亜科 (Sibley)|キジ]]、[[ライチョウ亜科 (Sibley)|ライチョウ類]]およびその仲間に加えて、[[ツカツクリ科|ツカツクリ類]]、[[ホウカンチョウ科]]の鳥およびその仲間)が含まれる。この分岐の起こった年代は、科学者により盛んに議論されている。真鳥亜綱が白亜紀に進化し、ほかの新顎類からキジカモ類が分かれたのが、[[K-T境界|K-T境界絶滅イベント]]の前であることについては意見の一致が見られたが、これ以外の新顎類の[[適応放散]]が起きたのが、鳥類以外の恐竜の絶滅以前であるのか、あるいは絶滅以降であったのかについては意見が異なる<ref name="Ericson">{{citation|last=Ericson |first=Per G.P. |month=December |year=2006 |title=Diversification of Neoaves: Integration of molecular sequence data and fossils |journal=[[w:Biology Letters|Biology Letters]] |volume=2 |issue=4 |pages=543–547 |doi=10.1098/rsbl.2006.0523 |pmid=17148284 |url=http://www.mrent.org/PDF/Ericson_et_al_2006_Neoaves.pdf |format=PDF |issn=1744-9561 |last2=Anderson |first2=CL |last3=Britton |first3=T |last4=Elzanowski |first4=A |last5=Johansson |first5=US |last6=Källersjö |first6=M |last7=Ohlson |first7=JI |last8=Parsons |first8=TJ |last9=Zuccon |first9=D |pmc=1834003}}</ref> 。この意見の不一致の原因は、部分的な証拠の相違によるものである。すなわち、化石記録の証拠が[[第三紀]]に適応放散が起きたことを示すにもかかわらず、分子年代測定は白亜紀の適応放散を示唆している。これらの証拠を調整しようとする試みでは、意見の分かれるところとなった<ref name="Ericson"/><ref>{{citation|last=Brown |first=Joseph W. |month=June |year=2007 |title=Nuclear DNA does not reconcile 'rocks' and 'clocks' in Neoaves: a comment on Ericson ''et al.'' |journal=[[w:Biology Letters|Biology Letters]] |volume=3 |issue=3 |pages=257–259 |doi=10.1098/rsbl.2006.0611 |pmid=17389215 |issn=1744-9561 |url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2464679/ |last2=Payne |first2=RB |last3=Mindell |first3=DP |pmc=2464679}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類の分類は議論の絶えない分野である。[[チャールズ・シブリー|シブリー]]と[[ジョン・アールクィスト|アールキスト]]の「[[シブリー・アールキスト鳥類分類]]」 ''Phylogeny and Classification of Birds'' (1990) は、鳥類の分類における画期的な業績であり<ref>{{Cite book|last=Sibley |first=Charles |authorlink=w:Charles Sibley |coauthors=[[ジョン・アールクィスト|Jon Edward Ahlquist]] |year=1990 |title=Phylogeny and classification of birds |location=New Haven |publisher=Yale University Press |isbn=0-300-04085-7}}</ref>、それは頻繁に議論され、絶えず修正されている。ほとんどの証拠は、分類における目 (order) の位置づけが正確であることを示唆するように見えたが<ref>{{Cite book|last=Mayr |first=Ernst |authorlink=w:Ernst W. Mayr |coauthors=Short, Lester L.|title=Species Taxa of North American Birds: A Contribution to Comparative Systematics |series=Publications of the Nuttall Ornithological Club, no. 9 |year=1970 |publisher=Nuttall Ornithological Club|location=Cambridge, Mass. |oclc=517185}}</ref>、2000年代後半に判明した分子系統により、いくつかの目分類は大幅な修正を受けた。目そのものの相互関係についても、研究者の意見は一致していない。現生鳥類の解剖学、化石、DNA などあらゆる証拠が問題解決のために用いられてきたが、強いコンセンサスは得られていない。しかし近年には、新たな化石や分子解析による証拠から、現生鳥類の目の進化に関して、徐々に新しい知見がもたらされるようになってきている。
| |
| − | | |
| − | === 現生鳥類の目分類 ===
| |
| − | {{See also|古顎類|新顎類}}
| |
| − | | |
| − | {{Cladogram
| |
| − | | cladogram =
| |
| − | {{clade|style=font-size:small; line-height:1em;
| |
| − | |label1=[[w:Neornithes|新鳥類]]
| |
| − | |{{clade
| |
| − | |[[古顎類]] {{sname||Paleognathae}}
| |
| − | |label2=[[新顎類]]
| |
| − | |{{clade
| |
| − | |[[キジカモ類]] {{sname||Galloanserae}}
| |
| − | |{{sname||Neoaves}}
| |
| − | }}
| |
| − | }}
| |
| − | }}
| |
| − | | caption = 現生鳥類の基系統 (basal) の多様化
| |
| − | }}
| |
| − | | |
| − | 以下の目分類は、[[国際鳥類学会]] (IOC) による目分類である。シブリー分類のような全面的な変更はないが、伝統的な目分類に対する修正により、ほぼ系統分類となっている。これらの修正は、初期の分子系統分類 [[シブリー・アールキスト分類|シブリーら (1990)]] や、最新の形態系統分類 Livezey & Zusi (2007) などと共通点は少ない<ref name="Hackett"/>。
| |
| − | | |
| − | 目レベルまでの系統は完全には解かれていないが、系統は、以下のような分類群が提案されている(ただし {{en|landbirds}} 〈陸鳥〉は正式な分類群ではない)。これらの系統は、有望な[[レトロポゾン]]によるものや<ref name="Suh">{{Cite journal | url=http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n8/full/ncomms1448.html |first=Alexander |last=Suh |last2=''et al''. | title=Mesozoic retroposons reveal parrots as the closest living relatives of passerine birds |journal=Nature |volume=2 |year=2011 |number=8 | doi=10.1038/ncomms1448 |accessdate=2014-06-25}}</ref>、近年の複数の研究 (Hackett, 2008<ref name="Hackett">{{Cite journal |last=Hackett |first=S.J. |last2=''et al.'' |date=2008-07-12|title=A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History |url=http://www.owlpages.info/downloads/A_Phylogenomic_Study_of_Birds_Reveals_Their_Evolutionary_History.pdf |format=PDF |journal=Science |volume=320 |issue=5884 |pages=1763-1768 |accessdate=2014-06-25}}</ref>; Mayr 2011<ref name="Mayr">{{Cite journal |last=Matr |first=Gerald |title=Metaves, Mirandornithes, Strisores and other novelties – a critical review of the higher-level phylogeny of neornithine birds |url=http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/abteilung/terrzool/ornithologie/metaves_review.pdf |format=PDF |journal=J. Zool. Syst. Evol. Res. | doi=10.1111/j.1439-0469.2010.00586.x | year=2011 | volume=49 | number=1 | page=58–76 |accessdate=2014-06-25}}</ref>) で支持されている。
| |
| − | | |
| − | {| class="wikitable" style="font-size:small"
| |
| − | | colspan="5" | [[古顎類]] {{sname||Palaeognathae}}
| |
| − | | [[シギダチョウ目]] {{sname||Tinamiformes}}、[[ダチョウ目]] {{sname||Struthioniformes}}、[[レア目]] {{sname||Rheiformes}}、[[ヒクイドリ目]] {{sname||Casuariiformes}}、[[キーウィ目]] {{sname||Apterygiformes}}
| |
| − | |-
| |
| − | | rowspan="9" | [[新顎類]]<br />{{sname||Neognathae}}
| |
| − | | colspan="4" | [[キジカモ類]] {{sname||Galloanserae}}
| |
| − | | [[キジ目]] {{sname||Galliformes}}、[[カモ目]] {{sname||Anseriformes}}
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="4" style="border-bottom:none" | {{sname||Neoaves}}
| |
| − | | [[ネッタイチョウ目]] {{sname||Phaethontiformes}}、[[サケイ目]] {{sname||Pteroclidiformes}}、[[クイナモドキ目]] {{sname||Mesitornithidae}}、[[ハト目]] {{sname||Columbiformes}}、[[ジャノメドリ目]] {{sname||Eurypygiformes}}、[[ツメバケイ目]] {{sname||Opisthocomiformes}}、[[ノガン目]] {{sname||Otidiformes}}、[[カッコウ目]] {{sname||Cuculiformes}}、[[ツル目]] {{sname||Gruiformes}}、[[エボシドリ目]] {{sname||Musophagiformes}}、[[チドリ目]] {{sname||Charadriiformes}}
| |
| − | |-
| |
| − | | rowspan="7" style="border-top:none" |
| |
| − | | colspan="3" | {{sname||Mirandornithes}}<ref>{{cite | last=Sangster | first=G. | year=2005 | doi=10.1111/j.1474-919x.2005.00432.x | title=A name for the flamingo-grebe clade | journal=[[:en:Ibis (journal)|Ibis]] | volume=147 | page=612–615 }}</ref>
| |
| − | | [[カイツブリ目]] {{sname||Podicipediformes}}、[[フラミンゴ目]] {{sname||Phoenicopteriformes}}
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="3" | {{sname|Strisores}}<ref name="Mayr"/>
| |
| − | | [[ヨタカ目]] {{sname||Caprimulgiformes}}、[[アマツバメ目]] {{sname||Apodiformes}}
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="3" | {{sname||Aequornithes}}<ref name="Mayr"/>
| |
| − | | [[アビ目]] {{sname||Gaviiformes}}、[[ペンギン目]] {{sname||Sphenisciformes}}、[[ミズナギドリ目]] {{sname||Procellariiformes}}、[[コウノトリ目]] {{sname||Ciconiiformes}}、[[ペリカン目]] {{sname||Pelecaniformes}}、[[カツオドリ目]] {{sname||Suliformes}}
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="3" style="border-bottom:none" | {{en|landbirds}}<ref name="Ericson"/>
| |
| − | | [[ノガンモドキ目]] {{sname||Cariamiformes}}、[[タカ目]] {{sname||Accipitriformes}}、[[フクロウ目]] {{sname||Strigiformes}}、[[ネズミドリ目]] {{sname||Coliiformes}}、[[オオブッポウソウ目]] {{sname||Leptosomatiformes}}、[[キヌバネドリ目]] {{sname||Trogoniformes}}
| |
| − | |-
| |
| − | | rowspan="3" style="border-top:none" |
| |
| − | | colspan="2" | {{sname||Picocoraciae}}<ref name="Mayr"/>
| |
| − | | [[サイチョウ目]] {{sname||Bucerotiformes}}、[[キツツキ目]] {{sname||Piciformes}}、[[ブッポウソウ目]] {{sname||Coraciiformes}}
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" style="border-bottom:none" | {{sname|Eufalconimorphae}}<ref name="Suh"/>
| |
| − | | [[ハヤブサ目]] {{sname||Falconiformes}}
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border-top:none" |
| |
| − | | {{sname||Psittacopasserae}}<ref name="Suh"/>
| |
| − | | [[オウム目]] {{sname||Psittaciformes}}、[[スズメ目]] {{sname||Passeriformes}}
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | [[ファイル:Neoaves Alternative Cladogram.png|thumb|400px|right|Neoaves の2つの姉妹群 Coronaves と Metaves<ref>[http://tolweb.org/Neoaves/26305 Tolweb.org], "Neoaves". ''Tree of Life Project''</ref>]]
| |
| − | | |
| − | 現生鳥類は[[古顎類]]と[[新顎類]]に分かれ、新顎類は[[キジカモ類]]と {{sname||Neoaves}} に分かれる。鳥類の現生種のうち、古顎類は0.5[[パーセント|%]]、キジカモ類は4.5%を占めるにすぎず、{{sname|Neoaves}} に種の95%が含まれる。
| |
| − | | |
| − | 古顎類は従来、[[胸骨]]に[[竜骨突起]]を残すシギダチョウ類と、竜骨突起を喪失した[[平胸類]](走鳥類〈[[ダチョウ目|ダチョウ類]]〉)に分けられてきたが、平胸類の単系統性が分子系統により否定された<ref>{{Cite journal |last=Harshman |first=John |last2=''et al''. |year=2008 |title=Phylogenomic evidence for multiple losses of flight in ratite birds |journal=Proc Natl Acad Sci |volume=105 |url=http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2533212 |accessdate=2014-06-28 }}</ref>。
| |
| − | | |
| − | {{sname|Neoaves}} は鳥類のなかで最も適応放散した群だが、その下位分類は確定していない。シブリーらを含む以前の試みのほとんどは、実際の系統を反映していないことが判明し、現在の分類に残っていない。Ericson ''et al.'' (2006)<ref name = "Ericson"/>は {{sname|Neoaves}} が2つの姉妹群 {{sname||Coronaves}} と {{sname||Metaves}} に分かれるとし、Hackett ''et al.'' (2008)<ref name="Hackett"/>にも弱く支持されたが、異論もある<ref name="Mayr"/>。
| |
| − | | |
| − | == 分布 ==
| |
| − | {{See also|{{仮リンク|地域別鳥類一覧|en|Lists of birds by region}}}}
| |
| − | [[ファイル:House sparrow04.jpg|thumb|left|alt= 模様のある翼と頭に、明るい色の腹と胸をした小さな鳥がコンクリートの上にいる。 |[[イエスズメ]]の生息域は人間の活動によって、劇的に拡大した<ref>{{Cite book|last=Newton |first=Ian|year=2003 |title=The Speciation and Biogeography of Birds |location=Amsterdam |publisher=Academic Press |isbn=0-12-517375-X|page=463}}</ref>。]]
| |
| − | 鳥類の生活と繁殖は、ほとんどの陸上生息地で営まれており、これらは7大陸すべてで見ることができる。その南限は[[ユキドリ]]の繁殖地で、[[南極大陸]]の内陸 {{convert|440|km|mi|-2|abbr=on}}におよぶ<ref>{{Cite book|last=Brooke |first=Michael |year=2004 |title=Albatrosses And Petrels Across The World |location=Oxford |publisher=Oxford University Press|isbn=0-19-850125-0|pages=}}</ref> 。最も高い鳥類の[[生物多様性|多様性]]は熱帯地方で起こっている。以前には、この高い多様性は熱帯でのより高い[[種分化]]の変化率によるものと考えられていたが、近年の研究では、高緯度地方の高い種分化の比率が、熱帯よりも大きい[[絶滅]]率によって、相殺されていることがわかった<ref>{{Cite journal |last=Weir |first=Jason T. |month=March |year=2007 |title=The Latitudinal Gradient in Recent Speciation and Extinction Rates of Birds and Mammals |journal=Science |volume=315 |issue=5818 |pages=1574–76 |doi=10.1126/science.1135590 |pmid=17363673 |issn=0036-8075 |last2=Schluter |first2=D}}</ref>。鳥類のさまざまな科が、世界中の海洋での生活にも適応しており、たとえば、ある種の[[海鳥]]は繁殖のときにだけ上陸し<ref name = "Burger">{{Cite book|last=Schreiber |first=Elizabeth Anne |coauthors=Joanna Burger |year=2001 |title=Biology of Marine Birds |location=Boca Raton |publisher=CRC Press |isbn=0-8493-9882-7|pages=}}</ref>、また、ある[[ペンギン|ペンギン類]]は {{convert|300|m|ft|-2|abbr=on}}以上潜水した記録を持ち<ref>{{Cite journal |last=Sato |first=Katsufumi |date=1 May 2002|title=Buoyancy and maximal diving depth in penguins: do they control inhaling air volume? |journal=Journal of Experimental Biology |volume=205 |issue=9 |pages=1189–1197 |pmid=11948196 |url=http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/205/9/1189 |issn=0022-0949 |author2=N |author3=K |author4=N |author5=W |author6=C |author7=B |author8=H |author9=L |accessdate=2014-06-28}}</ref>、ときに{{convert|500|m|ft|-2|abbr=on}}以上潜水して採餌するとされる<ref>{{Cite book|和書 |author=佐藤克文 |year=2011 |title=巨大翼竜は飛べたのか - スケールと行動の動物学 |publisher=[[平凡社]] |series = [[平凡社新書]] |isbn=978-4-582-85568-5 |pages=30-31頁、59頁}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類のなかには、人為的に[[外来種|移入]]された地域で、繁殖個体群を確立した種がいくつもある。これらの移入のなかには計画的になされたものもあり、たとえば[[コウライキジ]]は、[[狩猟]]鳥として世界中に移入された<ref>{{Cite book|last=Hill |first=David |coauthors=Peter Robertson |year=1988 |title=The Pheasant: Ecology, Management, and Conservation |location=Oxford |publisher=BSP Professional |isbn=0-632-02011-3|pages=}}</ref>。そのほか偶発的なものとしては、飼育下から逃げ出し(かご抜け)、北アメリカの複数の都市で野生化した[[オキナインコ]]の安定個体群の確立のような例もある<ref>{{cite web|last=Spreyer |first=Mark F.|coauthors=Enrique H. Bucher|year=1998|title=Monk Parakeet (Myiopsitta monachus)|work=The Birds of North America|publisher=Cornell Lab of Ornithology|url=http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/322 |doi=10.2173/bna.322 |accessdate=2014-06-28}}</ref>。また、[[アマサギ]]<ref>{{Cite journal |last=Arendt |first=Wayne J. |date=1988-01-01 |title=Range Expansion of the Cattle Egret, (''Bubulcus ibis'') in the Greater Caribbean Basin |journal=Colonial Waterbirds |volume=11 |issue=2 |pages=252–62 |doi=10.2307/1521007 |issn=07386028 |jstor=1521007}}</ref>、[[カラカラ (鳥)|キバラカラカラ]]<ref>{{Cite book|last=Bierregaard |first=R.O. |year=1994 |chapter=Yellow-headed Caracara |editor=Josep del Hoyo, Andrew Elliott and Jordi Sargatal (eds.) |title=[[w:Handbook of the Birds of the World|Handbook of the Birds of the World]]. Volume 2; New World Vultures to Guineafowl |location=Barcelona |publisher=Lynx Edicions |isbn=84-87334-15-6|pages=}}</ref>、[[モモイロインコ]]<ref>{{Cite book|last=Juniper |first=Tony |coauthors=Mike Parr |year=1998 |title=Parrots: A Guide to the Parrots of the World |location=London |publisher=[[w:Helm Identification Guides|Christopher Helm]] |isbn=0-7136-6933-0|pages=}}</ref>などのように、[[農業|耕作]]によって新たに作られた生息に適した地域に、元来の分布域をはるかに超えて{{仮リンク|鳥類の分布拡大|en| Avian range expansion|label=自然分布を拡大}}していった種もある。
| |
| − | | |
| − | == 解剖学と生理学 ==
| |
| − | {{Main|鳥類の体の構造|{{仮リンク|鳥類の視覚|en|Bird vision}}}}
| |
| − | [[ファイル:Birdmorphology.svg|thumb|300px|鳥類の典型的な外見的特徴。1:[[くちばし]]、2:頭頂、3:[[虹彩]]、4:[[瞳孔]]、5:[[上背]] ([[:en:Bird#Anatomy and physiology|Mantle]])、6:[[小雨覆]] ([[:en:Covert feather#Wing coverts|Lesser coverts]])、7:[[肩羽]] ([[:en:Scapular|Scapular]])、8:[[雨覆]] ([[:en:Covert feather#Wing coverts|Coverts]])、9:[[三列風切]] ([[:en:Tertials|Tertials]])、10:[[尾]]、11:[[初列風切]]、12:下腹、13:[[太股|腿]]、14:[[かかと]]、15:[[跗蹠]] ([[:en:Tarsus (skeleton)|Tarsus]])、16:[[趾 (鳥類)|趾]]、17:[[脛]]、18:[[腹]]、19:[[脇腹|脇]]、20:[[胸]]、21:[[喉]]、22:[[肉垂]] ([[:en:Wattle (anatomy)|Wattle]])、23:過眼線<!-- このキャプションに変更を加えるときは、この図にリンクしている他の記事でのキャプションも確認の上、変更してください。 -->]]
| |
| − | ほかの脊椎動物に比較して、鳥類は数多くの特異な適応を示すボディプラン ([[w:Body plan|body plan]]) を持っており、そのほとんどは{{仮リンク|鳥類の飛翔|en|Bird flight|label=飛翔}}を助けるためのものである。
| |
| − | | |
| − | === 骨格 ===
| |
| − | 骨格は非常に軽量な骨から構成されている。含気骨には大きな空気の満たされた空洞(含気腔)があり、[[呼吸器]]と結合している<ref>{{Cite book|和書 |editor=松岡廣繁・安部きみ子 |year=2009 |title=鳥の骨探 |publisher=NTS |series =BONE DESIGN SERIES |isbn=978-4-86043-276-8 |pages=18-19}}</ref><ref>{{cite web|last=Ehrlich |first=Paul R. |coauthors=David S. Dobkin, and Darryl Wheye |title=Adaptations for Flight |url=http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Adaptations.html |year=1988 |work=Birds of Stanford |publisher=[[スタンフォード大学|Stanford University]] |accessdate=2014-06-28}} ''The Birder's Handbook'' ([[パウル・エールリヒ|Paul Ehrlich]], David Dobkin, and Darryl Wheye. 1988. Simon and Schuster, New York.) に基づく</ref> 。成鳥の頭骨は癒合しており縫合線 ([[w:Suture (joint)|suture]]) がみられない<ref name=Gill_51>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、51頁</ref>。[[眼窩]]は大きく、骨{{仮リンク|中隔|en|Septum}}で隔てられている。[[脊椎]]には、頸(首)椎、胸椎、腰椎、尾椎の部位があり、頸椎は可動性が非常に高く、きわめて柔軟であるが、関節は[[胸椎]] ([[w:Thoracic vertebrae|thoracic vertebrae]]) 前部で減り、後部の脊椎骨にはない<ref>{{Cite news|title=The Avian Skeleton |url=http://www.paulnoll.com/Oregon/Birds/Avian-Skeleton.html |work=paulnoll.com |accessdate=2014-06-29}}</ref>。脊椎の最後のいくつかは[[骨盤]]と融合して{{仮リンク|複合仙骨|en|Synsacrum}}を形成する<ref name=Gill_28>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、28頁</ref>。飛べない鳥類をのぞいて、肋骨は平坦になっており、[[胸骨]]は飛翔のための筋肉を結合するために、船の[[竜骨 (船)|竜骨]]のような形状をしている。前肢は翼へと修正されている<ref>{{Cite web|title=Skeleton |url=http://fsc.fernbank.edu/Birding/skeleton.htm |work=Fernbank Science Center's Ornithology Web |accessdate=2014-06-29}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 消化、排泄、生殖 ===
| |
| − | 鳥類の[[消化器|消化器系]]は独特である。まず食べたものを一時的に貯蔵するための[[素嚢]](そのう)がある。素嚢の役割は種類によって異なり、食いだめをする種類や素嚢から吐き戻した食物や素嚢から分泌される[[素嚢乳]]を雛鳥に餌として与える種類がいるほかダチョウ類のように素嚢を持たない種類もいる<ref name=Dic_Ornithology_496>[[#鳥類学辞典|『鳥類学辞典』 (2004)]]、496頁</ref>。
| |
| − | 素嚢に蓄えられた食物は[[胃]]に送られるが、胃は前胃と筋胃の二つに分かれている。前胃は腺胃とも呼ばれ、内壁に多数の消化腺があり,消化酵素および酸性分泌物を出す。筋胃は[[砂嚢]](さのう)とも呼ばれ、筋肉が発達しているほか、飲み込んだ砂粒が入っており、この筋胃で食物をすりつぶすことで、歯のないことを補っている<ref>{{Cite journal |和書|author=[[和田勝]] |title=食べて消化する |date=2000-11 |publisher=[[文一総合出版]] |journal=Birder |volume=14 |number=11 |pages=8-9}}</ref><ref>{{Cite journal |last=Gionfriddo |first=James P. |date=1 February 1995|title=Grit Use by House Sparrows: Effects of Diet and Grit Size |journal=Condor |volume=97 |issue=1 |pages=57–67 |doi=10.2307/1368983 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v097n01/p0057-p0067.pdf |format=PDF |issn=00105422 |author2=Best |accessdate=2014-06-29}}</ref>。ほとんどの鳥類は、飛翔を助けるため、すばやく消化することに高度に適応している<ref name = "Attenborough">{{Cite book|last=Attenborough |first=David |authorlink=w:David Attenborough |year=1998 |title=[[w:The Life of Birds|The Life of Birds]] |location=Princeton |publisher=[[Princeton University Press]] |isbn=0-691-01633-X|pages=}}</ref>。渡りを行う鳥のなかには、腸の蛋白質といった、その体のいろいろな部分からの蛋白質を、渡りの間の補助的なエネルギー源として使用するようになっているものがある<ref name = "Battley">{{Cite journal |last=Battley |first=Phil F. |month=January |year=2000 |title=Empirical evidence for differential organ reductions during trans-oceanic bird flight |journal=[[w:Proceedings of the Royal Society|Proceedings of the Royal Society]] B |volume=267 |issue=1439 |pages=191–5 |doi=10.1098/rspb.2000.0986 |pmid=10687826 |issn=0962-8452 |last2=Piersma |first2=T |last3=Dietz |first3=MW |last4=Tang |first4=S |last5=Dekinga |first5=A |last6=Hulsman |first6=K |pmc=1690512}} (Erratum in ''Proceedings of the Royal Society B'' '''267'''(1461):2567.)</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類は[[爬虫類]]と同様に、基本的には尿酸排泄性である。すなわち、その[[腎臓]]は血液中の窒素廃棄物を抽出して、これを[[尿素]]もしくは[[アンモニア]]ではなく、[[尿酸]]として尿管を経由して腸に排出する。鳥類には[[膀胱]]ないし外部尿道孔がなく(ただしダチョウは例外である)、このため尿酸は半固体の廃棄物として、糞と一緒に排泄される<ref>{{cite web|last=Ehrlich |first=Paul R. |coauthors=David S. Dobkin, and Darryl Wheye |title=Drinking |url=http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Drinking.html |year=1988 |work=Birds of Stanford |publisher=Standford University |accessdate=2014-06-29}}</ref><ref>{{Cite journal |last=Tsahar |first=Ella |title=Can birds be ammonotelic? Nitrogen balance and excretion in two frugivores |journal=Journal of Experimental Biology |volume=208 |issue=6 |pages=1025–34 |year=2005 |pmid=15767304 |doi=10.1242/jeb.01495 |month= March|issn=0022-0949 |url=http://jeb.biologists.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15767304 |last2=Martínez Del Rio |first2=C |last3=Izhaki |first3=I |last4=Arad |first4=Z }}</ref><ref name=coprodeum>{{cite journal | doi= 10.1016/S1095-6433(03)00006-0 | last1= Skadhauge | first1= E | last2= Erlwanger | first2= KH | last3= Ruziwa | first3= SD | last4= Dantzer | first4= V | last5= Elbrønd | first5= VS | last6= Chamunorwa | first6= JP | title= Does the ostrich (''Struthio camelus'') coprodeum have the electrophysiological properties and microstructure of other birds? | journal= Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology | volume= 134 | issue= 4 | pages= 749–755 | year= 2003 | pmid = 12814783 }}</ref>。ただしハチドリのような鳥類は、条件的アンモニア排泄性であり、ほとんどの窒素廃棄物をアンモニアとして排出することができる<ref>{{Cite journal |last=Preest |first=Marion R. |month=April |year=1997 |title=Ammonia excretion by hummingbirds |journal=Nature |volume=386 |issue= 6625|pages=561–62 |doi=10.1038/386561a0 |last2=Beuchat |first2=Carol A.}}</ref>。さらに鳥類は、[[哺乳類]]が[[クレアチニン]]を排泄するのに対して、[[クレアチン]]を排泄する<ref name = "Gill">{{Cite book|last=Gill |first=Frank |authorlink=w:Frank Gill (ornithologist) |year=1995 |title=Ornithology |publisher=WH Freeman and Co |location=New York |isbn=0-7167-2415-4 |pages=}}</ref>。この物質は、ほかの腸の産生物と同じように[[総排出腔]]から出る<ref>{{Cite journal |last=Mora |first=J. |year=1965 |title=The Regulation of Urea-Biosynthesis Enzymes in Vertebrates |journal=[[w:Biochemical Journal|Biochemical Journal]] |volume=96 |pages=28–35 |pmid=14343146 |url=http://www.biochemj.org/bj/096/0028/0960028.pdf |format=PDF |month= July|issn=0264-6021 |last2=Martuscelli |first2=J |last3=Ortiz Pineda |first3=J |last4=Soberon |first4=G |pmc=1206904}}</ref><ref>{{Cite journal |last=Packard |first=Gary C.|year=1966 |title=The Influence of Ambient Temperature and Aridity on Modes of Reproduction and Excretion of Amniote Vertebrates |journal=[[w:The American Naturalist|The American Naturalist]] |volume=100 |issue=916 |pages=667–82 |doi=10.1086/282459 |jstor=2459303}}</ref>。総排出腔は多目的の開口部で、排泄物はこれを通して排出され、鳥が交尾するときにはそれぞれの[[鳥類の体の構造#生殖器系|総排出腔を接触]]させ、そして雌はそこから卵を産む。これに加えて、多くの種が[[ペリット]](ペレット、pellet)の吐き戻しを行う<ref>{{Cite journal |last=Balgooyen |first=Thomas G. |date=1 October 1971|title=Pellet Regurgitation by Captive Sparrow Hawks (''Falco sparverius'') |journal=[[w:Condor (journal)|Condor]] |volume=73 |issue=3 |pages=382–85 |doi=10.2307/1365774 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v073n03/p0382-p0385.pdf |format=PDF |issn=00105422 |jstor=1365774 |accessdate=2014-06-29}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 呼吸器 ===
| |
| − | 鳥類は、すべての動物群のなかで、最も複雑な[[呼吸器]]を持ったグループのひとつである<ref name = "Gill"/>。鳥が息を吸うとき、新鮮な空気の75%が肺を迂回して、後部 [[気嚢]]に直接流れ込み、これを空気で満たす。後部気嚢とは、肺から広がって骨のなかの気室(含気腔)に繋がっている気嚢のグループである。残りの25%の空気は直接肺に行く。鳥が息を吐くときには、使われた空気が肺から排出され、同時に、後部気嚢に蓄えられていた新鮮な空気が肺に送り込まれる。このようにして、鳥類の肺には息を吸うときにも吐くときにも、常時新鮮な空気が供給されている<ref>{{Cite journal |last=Maina |first=John N. |month=November |year=2006 |title=Development, structure, and function of a novel respiratory organ, the lung-air sac system of birds: to go where no other vertebrate has gone |journal=Biological Reviews |volume=81 |issue=4 |pages=545–79 |pmid=17038201 |doi=10.1017/S1464793106007111 |issn=1464-7931}}</ref>。鳥の声は、[[鳴管]]を使って作り出されている。鳴管は筋肉質の鼓室であり、気管の下部末端から分岐し、複数の鼓形膜が組み合わされている<ref>{{Cite journal |和書|author=和田勝 |title=さえずるってどうゆうこと |date=2001-10 |publisher=文一総合出版 |journal=Birder |volume=15 |number=10 |pages=64-65}}</ref><ref name = "Suthers">{{Cite book|last=Suthers |first=Roderick A. |coauthors=Sue Anne Zollinger |chapter=Producing song: the vocal apparatus |editor=H. Philip Zeigler and Peter Marler (eds.) |year=2004 |title=Behavioral Neurobiology of Birdsong |series=Annals of the New York Academy of Sciences '''1016''' |location=New York |publisher=New York Academy of Sciences |isbn=1-57331-473-0 |pages=109–129 |doi=10.1196/annals.1298.041}} PMID 15313772</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 循環器 ===
| |
| − | 鳥類の心臓は、哺乳類と同じく4室(二心房二心室)あり<ref name=Gill_162>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、162頁</ref>、右側の[[大動脈弓]]より[[体循環]]が起こるが、哺乳類では鳥類と異なり左側の大動脈弓による<ref name = "Gill"/><ref>{{Cite journal |和書|author=和田勝 |title=血の巡りをよく |date=2000-12 |publisher=文一総合出版 |journal=Birder |volume=14 |number=12 |pages=8-9}}</ref>。下大静脈は、腎門脈系を経由して、四肢からの血流を受け取る。哺乳類とは異なり、鳥類の[[赤血球]]には[[細胞核|核]]がある<ref>{{Cite journal |和書|author=和田勝 |title=赤い血が流れて |date=2001-01 |publisher=文一総合出版 |journal=Birder |volume=15 |number=1 |pages=66-68}}</ref><ref>{{Cite journal |last=Scott |first=Robert B. |month=March |year=1966 |title=Comparative hematology: The phylogeny of the erythrocyte |journal=Annals of Hematology |volume=12 |issue=6 |pages=340–51 |doi=10.1007/BF01632827 |pmid=5325853 |issn=0006-5242}}</ref>。[[ニワトリ]]の[[血糖値]]は210-240mg/dlであり、鳥類は[[哺乳類]]に比べて2-3倍の血糖値を示す<ref>芝田 猛、渡辺 誠喜、ウズラの成長に伴う血糖値の変化と血糖成分、日本畜産学会報 Vol. 52 (1981) No.12、P 869-873、http://doi.org/10.2508/chikusan.52.869</ref>
| |
| − | | |
| − | === 知覚 ===
| |
| − | [[ファイル:Bird blink-edit.jpg|thumb|left|300px| [[ズグロトサカゲリ]]の目を覆う[[瞬膜]]。]]
| |
| − | [[神経系]]は、鳥類の体の大きさから見ると相対的に大きい<ref name=Gill_208-209>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、208-209頁</ref>。脳において最も発達しているのは、飛翔に関連した機能を司る部位であり、[[小脳]]が運動を調節する一方、[[大脳]]が行動パターンや航法、繁殖行動、営巣などをコントロールする。ほとんどの鳥が貧弱な[[嗅覚]]しか持たないが、顕著な例外として[[キーウィ (鳥)|キーウィ類]]<ref>{{Cite journal |last=Sales |first=James |year=2005 |title=The endangered kiwi: a review |journal=Folia Zoologica |volume=54 |issue=1–2 |pages=1–20 |url=http://www.ivb.cz/folia/54/1-2/01-20.pdf |format=PDF |accessdate=2014-07-01}}</ref>、[[コンドル科|コンドル類]]<ref name="Avian Sense of Smell">{{cite web|last=Ehrlich |first=Paul R. |coauthors=David S. Dobkin, and Darryl Wheye |title=The Avian Sense of Smell |url=http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Avian_Sense.html |year=1988 |work=Birds of Stanford |publisher=Standford University |accessdate=2014-07-01}}</ref>および[[ミズナギドリ目]]<ref>{{Cite journal |last=Lequette |first=Benoit |date=1 August 1989|title=Olfaction in Subantarctic seabirds: Its phylogenetic and ecological significance |journal=The Condor |volume=91 |issue=3 |pages=732–35 |doi=10.2307/1368131 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v091n03/p0732-p0735.pdf |format=PDF |issn=00105422 |author2=Verheyden |author3=Jouventin}}</ref>の鳥などがあげられる。鳥類の[[視覚]]システムは一般に高度に発達している。水鳥は特別に柔軟なレンズを持つことで、空気中の視覚と水中の視覚を両立させている<ref name=Gill_195>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、195頁</ref>。なかには2つの中心窩を持つ種もいる<ref>{{Cite journal |last=Wilkie |first=Susan E. |year=1998 |title=The molecular basis for UV vision in birds: spectral characteristics, cDNA sequence and retinal localization of the UV-sensitive visual pigment of the budgerigar (''Melopsittacus undulatus'') |journal=[[w:Biochemical Journal|Biochemical Journal]] |volume=330 |pages=541–47 |pmid=9461554 |month= February|issn=0264-6021 |url=http://www.biochemj.org/bj/330/0541/bj3300541.htm |last2=Vissers |first2=PM |last3=Das |first3=D |last4=Degrip |first4=WJ |last5=Bowmaker |first5=JK |last6=Hunt |first6=DM |pmc=1219171}}</ref>。鳥類は[[4色型色覚]]であり、赤、緑、青の[[錐体細胞]]と同じように、[[紫外線]] (UV) に感度のある錐体細胞を[[網膜]]に持っている。これによりかれらは紫外線を見分けることができ、それは求愛行動にも関係する。多くの鳥類は、紫外線による羽衣(うい)の模様を示すが、これはヒトの目には見えない。すなわち、ヒトの肉眼では雌雄が同じに見えるような鳥でも、その羽毛に紫外線を反射する斑の存在によって見分けられる。雄の[[アオガラ]]の羽毛には、紫外線を反射する冠状の斑があり、求愛行動の際にはポーズを取り、その頸部の羽毛を立てることでディスプレイを行う<ref>{{Cite journal |last=Andersson|first=S.|coauthors=J. Ornborg and M. Andersson |title=Ultraviolet sexual dimorphism and assortative mating in blue tits|journal=Proceeding of the Royal Society B |year=1998 |volume=265 |issue=1395 |pages=445–50 |doi=10.1098/rspb.1998.0315}}</ref>。紫外線はまた、餌を採ることにも使用されている。[[チョウゲンボウ]]の仲間は、[[齧歯類]]が地上に残した紫外線を反射する尿の痕跡を見つけることで獲物を探すことが証明されている<ref>{{Cite journal |last=Viitala |first=Jussi |year=1995 |journal=Nature |volume=373 |issue=6513 |pages=425–27 |title=Attraction of kestrels to vole scent marks visible in ultraviolet light |doi=10.1038/373425a0 |last2=Korplmäki |first2=Erkki |last3=Palokangas |first3=Pälvl |last4=Koivula |first4=Minna}}</ref> 。鳥類のまぶたは、瞬きには使用されない。そのかわりに目は、水平方向に移動する3番目のまぶたである[[瞬膜]]によって潤滑されている<ref>{{Cite journal |last=Williams |first=David L. |month=March |year=2003 |title=Symblepharon with aberrant protrusion of the nictitating membrane in the snowy owl (''Nyctea scandiaca'') |journal=Veterinary Ophthalmology |volume=6 |issue=1 |pages=11–13 |doi=10.1046/j.1463-5224.2003.00250.x |pmid=12641836 |issn=1463-5216 |last2=Flach |first2=E}}</ref>。また、多くの水鳥において、瞬膜は目を覆う[[コンタクトレンズ]]のような働きをする<ref name=Gill_194-195>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、194-195頁</ref>。鳥類の網膜は、櫛状体(櫛状突起、[[w:Pecten oculi|pecten]])と呼ばれる扇状の血液供給システムを持っている<ref name=Gill_197-198>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、197-198頁</ref>。ほとんどの鳥は眼球を動かすことができないが、[[カワウ]]のような例外もある<ref>{{Cite journal |last=White |first=Craig R. |month=July |year=2007 |title=Vision and Foraging in Cormorants: More like Herons than Hawks? |journal=PLoS ONE |volume=2 |issue=7 |pages=e639 |doi=10.1371/journal.pone.0000639 |pmid=17653266 |last2=Day |first2=N |last3=Butler |first3=PJ |last4=Martin |first4=GR |pmc=1919429 |last5=Bennett |first5=Peter|editor1-last=Bennett|editor1-first=Peter}}</ref>。鳥類のうち、目をその頭部の側面に持つものは広い[[視野]] ([[w:Visual field|visual field]]) を持ち、フクロウのように頭部の前面に両目があるものは、{{仮リンク|双眼視覚|en|Binocular vision}}を持ち、[[被写界深度]]を見積もることができる<ref>{{Cite journal |last=Martin |first=Graham R. |year=1999 |title=Visual fields in Short-toed Eagles, ''Circaetus gallicus'' (Accipitridae), and the function of binocularity in birds |journal=Brain, Behaviour and Evolution |volume=53 |issue=2 |pages=55–66 |doi=10.1159/000006582 |pmid= 9933782 |issn=0006-8977 |last2=Katzir |first2=G}}</ref>。鳥類の[[耳]]には外側の[[耳介]]はなく、耳羽(じう)という羽毛に覆われているが<ref name=Gill_200>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、200頁</ref>、[[フクロウ科|フクロウ類]]の{{仮リンク|トラフズク属|en|Asio}}、{{仮リンク|ワシミミズク属|en|Horned owl}}、{{仮リンク|コノハズク属|en|Scops owl}}ような鳥では、頭部の羽毛が耳のように見える房(羽角、うかく)を形成する。[[内耳]]には[[蝸牛]](かぎゅう)があるが、哺乳類のような螺旋状ではない<ref>{{Cite journal |last=Saito |first=Nozomu |year=1978 |title=Physiology and anatomy of avian ear |journal=The Journal of the Acoustical Society of America |volume=64 |issue=S1 |pages=S3 |doi=10.1121/1.2004193}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 化学的防御 ===
| |
| − | 数種の鳥類は、捕食者に対して化学的防御を用いることができる。一部の[[ミズナギドリ目]]の鳥は、攻撃者に対して不快な油状の胃液 ([[w:Stomach oil|Stomach oil]]) を吐き出すことができ<ref>{{Cite journal |last=Warham |first=John |date=1 May 1977|title=The Incidence, Function and ecological significance of petrel stomach oils |journal=Proceedings of the New Zealand Ecological Society |volume=24 |pages=84–93 |url=http://www.newzealandecology.org/nzje/free_issues/ProNZES24_84.pdf |format=PDF |doi=10.2307/1365556 |issn=00105422 |issue=3 |jstor=1365556 |accessdate=2014-07-04}}</ref>、また、[[ニューギニア島|ニューギニア]]産の数種の[[ピトフーイ|ピトフーイ(ピトフィ)類]](モリモズ類)の数種は、その皮膚や羽毛などに強力な神経毒を持っており<ref name=Yamashina2006_174-177>[[#山階2006|山階鳥研 (2006)]]、174-177頁</ref><ref>{{Cite journal |last=Dumbacher |first=J.P. |month=October |year=1992 |title=Homobatrachotoxin in the genus ''Pitohui'': chemical defense in birds? |journal=Science |volume=258 |issue=5083 |pages=799–801 |doi=10.1126/science.1439786 |pmid=1439786 |issn=0036-8075 |last2=Beehler |first2=BM |last3=Spande |first3=TF |last4=Garraffo |first4=HM |last5=Daly |first5=JW}}</ref>、これは寄生虫に対する防御と考えられている<ref name=Yamashina2006_175>[[#山階2006|山階鳥研 (2006)]]、175頁</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 性 ===
| |
| − | 鳥類には2つの性別、すなわち雄と雌がある。鳥類の性は、哺乳類が持っているXとYの染色体ではなく、[[Z染色体|ZとWの性染色体]]によって決定される。雄の鳥は、2つのZ染色体 (ZZ) を持ち、雌の鳥はW染色体とZ染色体 (WZ) を持っている<ref name=Gill_401-402>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、401-402頁</ref>。鳥類のほとんどすべての種において、個々の性別は受精の際に決定される。しかしながら、最近の研究によって、[[ヤブツカツクリ]]では、孵化中の温度が高いほど、雌に対する雄の[[性比]]が高くなったことから、[[性決定#温度依存性決定|温度依存性決定]] ([[w:Temperature-dependent sex determination|Temperature-dependent sex determination]]) が証明された<ref>{{Cite journal |last=Göth|first=Anne|title=Incubation temperatures and sex ratios in Australian brush-turkey (''Alectura lathami'') mounds|journal=Austral Ecology|year=2007|volume=32|issue=4|pages=278–85|doi=10.1111/j.1442-9993.2007.01709.x}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 羽毛、羽衣と鱗 ===
| |
| − | {{Main|羽毛|風切羽}}
| |
| − | [[ファイル:African Scops owl.jpg|alt= 目を閉じたフクロウが、同じような色をした木の幹の前にいる。部分的に木の葉に隠れている。|thumb|left|{{仮リンク|アフリカコノハズク|en|African scops owl}}は羽衣によって、周囲の風景に溶け込むことができる。]]
| |
| − | | |
| − | 羽毛は(現在では真の鳥類であるとは考えられていない[[羽毛恐竜|恐竜の一部]]にも存在するが)、鳥類に特有の特徴である。羽毛によって飛翔が可能になり、断熱によって[[体温#体温調節|体温調節]] ([[w:Thermoregulation|thermoregulation]]) を助け、そしてディスプレイやカモフラージュ、情報伝達にも使用される<ref name=Gill_100>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、100頁</ref>。羽毛にはいくつもの種類があり、それぞれが、個々のさまざまな目的に応じて機能している。羽毛は皮膚に付属した上皮成長物であり、羽域(羽区、pterylae)と呼ばれる、皮膚の特定の領域にのみ生ずる<ref name="Shigeta199708">{{Cite journal |和書|author=茂田良光 |title=鳥類の羽毛と換羽 |date=1997-8 |publisher=文一総合出版 |journal=BIRDER |volume=11 |number=8 |pages=27-33}}</ref>。これらの羽域の分布パターン(羽区分布、pterylosis)は分類学や系統学で使用されている。鳥の体における羽毛の配列や外観を総称して、羽衣 ([[w:Plumage|plumage]]) と呼ぶ<ref name="Shigeta199708"/>。羽衣は、同一種のなかでも、年齢、[[社会的地位]]<ref>{{Cite journal |last=Belthoff |first=James R. |date=1 August 1994|title=Plumage Variation, Plasma Steroids and Social Dominance in Male House Finches |journal=The Condor |volume=96 |issue=3 |pages=614–25 |doi=10.2307/1369464 |issn=00105422 |author2=Dufty, |author3=Gauthreaux,}}</ref>、[[性的二形|性別]]によって変化することがある<ref>{{cite web|last=Guthrie| first=R. Dale|title=How We Use and Show Our Social Organs |work=Body Hot Spots: The Anatomy of Human Social Organs and Behavior |url=http://employees.csbsju.edu/lmealey/hotspots/chapter03.htm |accessdate=2014-07-05 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20070621225459/http://employees.csbsju.edu/lmealey/hotspots/chapter03.htm |archivedate = June 21, 2007}}</ref> 。
| |
| − | | |
| − | 羽衣は定期的に生え変わっている(換羽、[[w:Moulting|moult]])。鳥の標準的な羽衣は、繁殖期のあとに換羽したものであり、非繁殖羽 (Non-breeding plumage) として知られている。あるいはハンフリー・パークスの用語 ([[w:Humphrey-Parkes terminology|Humphrey-Parkes terminology]]) によれば「基本」羽 ("basic" plumage) である。繁殖羽、あるいは基本羽の変化したものは、ハンフリー・パークスの用語法によれば「交換」羽 ("alternate" plumages) として知られる<ref>{{Cite journal |last=Humphrey |first=Philip S. |date=1 June 1959|title=An approach to the study of molts and plumages |journal=The Auk |volume=76 |pages=1–31 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Auk/v076n01/p0001-p0031.pdf |format=PDF |doi=10.2307/3677029 |issn=09088857 |issue=2 |jstor=3677029 |accessdate=2014-07-05}}</ref>。ほとんどの種で、換羽は年1回起こるが、なかには年2回換羽するものもあり、また、大型の猛禽類は、何年かに1回だけ生え変わるものもある。換羽のパターンは種ごとに異なる。[[スズメ目]]の鳥に見られる一般的なパターンは、初列風切が外側に向かって(遠心性換羽)、次列風切は内側に向かって(求心性換羽)<ref name="Shigeta199708"/>、そして尾羽が中央から外側に向かって生え変わっていく(遠心性換羽)<ref name=Gill_129 /><ref>{{cite web|first=Robert B|last=Payne|title=Birds of the World, Biology 532|url=http://www.ummz.umich.edu/birds/resources/families_otw.html|publisher=Bird Division, University of Michigan Museum of Zoology|accessdate=2007-10-20}}</ref>。スズメ目の鳥では、[[風切羽]]は、最も内側の初列風切から始まり、一度に左右1枚ずつ生え変わる。初列風切の内側半分(6番目の第5羽)が生え変わると、最も外側の三列風切が抜け始める。最も内側の三列風切が換羽したあと、次列風切が最も外側から抜け始め、これがより内側の羽毛へと進行していく。初列雨覆は、それが覆っている初列風切の換羽に合わせて生え変わる<ref name="Shigeta199708"/><ref name="pettingill">{{Cite book|author=Pettingill Jr. OS|year=1970|title=Ornithology in Laboratory and Field|isbn=808716093|publisher=Burgess Publishing Co}}</ref>。[[ハクチョウ|ハクチョウ類]]<ref name=Yamashina2004_64-66>[[#山階2004|山階鳥研 (2004)]]、65頁</ref>、[[雁|ガン類]]、[[カモ|カモ類]]といった種は、すべての風切羽が一度に抜け、一時的に飛ぶことができなくなるほか<ref name="debeeretal">{{cite web|url= http://web.uct.ac.za/depts/stats/adu/pdf/ringers-manual.pdf |format=PDF |year=2001 |author=de Beer SJ, Lockwood GM, Raijmakers JHFS, Raijmakers JMH, Scott WA, Oschadleus HD, Underhill |title=SAFRING Bird Ringing Manual |page=60 |accessdate=2014-07-05}} </ref>[[アビ属|アビ類]]<ref name=Yamashina2004_64-66 />、[[ヘビウ属|ヘビウ類]]、[[フラミンゴ|フラミンゴ類]]、[[ツル|ツル類]]、[[クイナ科|クイナ類]]、 [[ウミスズメ科|ウミスズメ類]]にもこのような種がある<ref name="Shigeta199708"/>。一般的な様式として、尾羽の脱落と生え変わりは、最も内側の一対から始まる<ref name="pettingill"/>。しかし、[[キジ科]]の[[セッケイ|セッケイ類]]においては、外側尾羽の中心から換羽が始まり、双方向への進行が見られる<ref name=Gill_129>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、129頁</ref>。[[キツツキ科|キツツキ類]]や[[キバシリ科|キバシリ類]]の尾羽では、遠心性換羽は少し変更され、これらの換羽は内側から2番目の一対の尾羽から始まり、そして一対の中央尾羽で終わる。これによって木をよじ登るのための尾羽の機能を維持している<ref name="pettingill"/><ref>{{Cite journal |first1=Mayr |last1=Ernst |first2=Mayr |last2=Margaret |year=1954|title=The tail molt of small owls |journal=The Auk |volume=71 |issue=2 |pages=172–178 |url=http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/auk/v071n02/p0172-p0178.pdf |format=PDF |accessdate=2014-07-05}}</ref>。営巣に先立って、ほとんどの鳥類の雌は、腹に近い羽毛を失うことで、皮膚の露出した{{仮リンク|抱卵斑|en|Brood patch}}を得る。この部分の皮膚は血管がよく発達し、鳥の抱卵の助けになる<ref name=Gill_450-451>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、450-451頁</ref><ref>{{Cite journal |last=Turner |first=J. Scott |year=1997 |title=On the thermal capacity of a bird's egg warmed by a brood patch |journal=Physiological Zoology |volume=70 |issue=4 |pages=470–80 |doi=10.1086/515854 |pmid=9237308 |month= July|issn=0031-935X}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | [[ファイル:Red Lory (Eos bornea)-6.jpg|alt= 黄色のくちばしをした赤いインコが翼の羽をくわえている。|upright|right|thumb|ヒインコ (''[[w:Eos bornea|Eos bornea]]'') の羽繕い]]
| |
| − | 羽毛はメンテナンスが必要であり、鳥類は毎日、羽繕いや手入れを行い、かれらは日常の9%前後をこの作業に費やしている<ref>{{Cite journal |last=Walther |first=Bruno A. |year=2005 |title=Elaborate ornaments are costly to maintain: evidence for high maintenance handicaps |journal=Behavioural Ecology |volume=16 |issue=1 |pages=89–95 |doi=10.1093/beheco/arh135}}</ref>。くちばしは、羽毛から異物のかけらを払い出すだけではなく、{{仮リンク|尾腺|en|Uropygial gland}}からの[[蝋]]のような分泌物を塗ることにも使われる。この分泌物は羽毛の柔軟性を守り、[[抗菌薬]]としても働き、羽毛を劣化させる[[細菌]]の成長を阻害する<ref>{{Cite journal |last=Shawkey |first=Matthew D. |year=2003 |title=Chemical warfare? Effects of uropygial oil on feather-degrading bacteria |journal=[[w:Journal of Avian Biology|Journal of Avian Biology]] |volume=34 |issue=4 |pages=345–49 |doi=10.1111/j.0908-8857.2003.03193.x |last2=Pillai |first2=Shreekumar R. |last3=Hill |first3=Geoffrey E.}}</ref>。この作用は、アリの分泌する[[ギ酸]]によって補われているとされ、鳥類は羽毛の寄生虫を取り除くために、[[蟻浴]]として知られている行動を通してこれを得ると考えられている<ref>{{Cite journal |last=Ehrlich |first=Paul R. |year=1986 |title=The Adaptive Significance of Anting |journal=The Auk |volume=103 |issue=4 |page=835 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Auk/v103n04/p0835-p0835.pdf |format=PDF}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類においては、羽毛が[[紫外線]]の皮膚への到達を妨げている。鳥類は、皮膚から[[皮脂]]を分泌し、羽毛を[[グルーミング|羽繕い]]することによって口から[[ビタミンD]]を摂取しているとの説もある。この説は毛皮を有する哺乳類にも該当する<ref>{{cite book |first1=Sam D. |last1=Stout |first2=Sabrina C. |last2=Agarwal |last3=Stout |first3=Samuel D. |title=Bone loss and osteoporosis: an anthropological perspective |publisher=Kluwer Academic/Plenum Publishers |location=New York |year=2003 |isbn=0-306-47767-X}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類の[[鳥類の体の構造#鱗|鱗]](うろこ)は、くちばしや、鉤爪、蹴爪と同じくケラチンから作られている。鱗は主に[[趾 (鳥類)|趾]](あしゆび)や跗蹠(ふしょ)に見られるが、種によっては踵(かかと)のずっと上の部位まで見られるものもある。[[カワセミ科|カワセミ類]]や[[キツツキ科|キツツキ類]]を除いて、大部分の鳥の鱗はほとんど重なっていない。鳥類の鱗は、爬虫類や哺乳類のものと[[相同|相同性]]であると考えられている<ref>{{Cite book|last=Lucas |first=Alfred M. |year=1972 |title=Avian Anatomy—integument |location=East Lansing, Michigan, US |publisher=USDA Avian Anatomy Project, Michigan State University |pages=67, 344, 394–601}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | == 飛翔 ==
| |
| − | {{See also|飛翔|{{仮リンク|鳥類の飛翔|en|Bird flight}}}}
| |
| − | [[ファイル:Restless flycatcher04.jpg|left|alt= 白い胸をした黒い鳥が翼を下に降り下ろして、広がった尾羽を下に向けて飛んでいる。| thumb|羽ばたき飛翔で翼を打ち下ろす{{仮リンク|フタイロヒタキ|en|Restless Flycatcher}}。]]
| |
| − | ほとんどの鳥は{{仮リンク|動物の飛行と滑空|en|Flying and gliding animals|label=飛翔}}することができ、このことが鳥類を、他のほとんどすべての脊椎動物の綱から際立たせている。飛翔はほとんどの種の鳥にとって第一の移動手段であり、繁殖、採餌、そして捕食者からの回避と脱出に用いられる。鳥類は、[[翼型|飛行翼]]として機能するように修正された前肢([[翼]])ばかりではなく<ref name=Gill_131-138>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、131-138頁</ref>、軽量な骨格構造や<ref name=Gill_27・147>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、27頁、147頁</ref>、2つの大きな飛翔のための筋肉(飛翔筋、鳥の全体重の20%以上を占める<ref name=Dic_Ornithology_698>[[#鳥類学辞典|『鳥類学辞典』 (2004)]]、698頁</ref>)である[[大胸筋]]と烏口上筋(うこうじょうきん)といった飛行のためのさまざまな適応が見られる<ref name=Gill_149-151>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、149-151頁</ref>。これに付随して、胸骨に竜骨突起(竜骨稜)が発達すること、脊椎骨や腰骨が癒合すること、尾椎の癒合による尾端骨なども飛翔への適応の一部をなしている<ref name=Gill_28>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、28頁</ref>。短い消化管は体内に蓄積する食物を少なくし、尿酸による排出も排出物の蓄積を減らすことで体の軽量化に貢献する。なお、羽毛や気嚢などは飛行能力の発達に先立って恐竜が持っていたと考えられ、これらは[[前適応]]の例である。
| |
| − | | |
| − | 翼の形状と大きさは、一般的に鳥の飛翔のタイプによって決まる<ref name=Gill_146-147>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、146-147頁</ref>。多くの鳥は、力の必要な羽ばたきによる飛翔と、よりエネルギー要求の低い帆翔(ソアリング、soaring)による飛翔を組み合わせている。
| |
| − | | |
| − | 多くの絶滅種であったような[[飛べない鳥]]は、約60種が現存している<ref>{{Cite book|last=Roots |first=Clive |year=2006 |title=Flightless Birds |location=Westport |publisher=Greenwood Press |isbn=978-0-313-33545-7|pages=}}</ref>。飛行能力の消滅は、隔絶された島嶼の鳥類にしばしば起きるが、おそらくこれは限られた資源と、陸棲の捕食者の不在による<ref>{{Cite journal |last=McNab |first=Brian K. |month=October |year=1994 |title=Energy Conservation and the Evolution of Flightlessness in Birds |journal=The American Naturalist |volume=144 |issue=4 |pages=628–42 |doi=10.1086/285697 |jstor=2462941}}</ref>。[[ペンギン|ペンギン類]]は飛行こそしないが、[[ウミスズメ科|ウミスズメ類]]、[[ミズナギドリ科|ミズナギドリ類]]、[[カワガラス科|カワガラス類]]など、飛翔する鳥類が翼を使って水中を泳ぐ場合と同様の筋肉を使い、水中を「飛行」する<ref>{{Cite journal |last=Kovacs |first=Christopher E. |month=May |year=2000 |title=Anatomy and histochemistry of flight muscles in a wing-propelled diving bird, the Atlantic Puffin, ''Fratercula arctica'' |journal=Journal of Morphology |volume=244 |issue=2 |pages=109–25|doi=10.1002/(SICI)1097-4687(200005)244:2<109::AID-JMOR2>3.0.CO;2-0 |pmid=10761049 |last2=Meyers |first2=RA }}</ref>。
| |
| − | | |
| − | == 生態 ==
| |
| − | 鳥類はほとんどが[[昼行性]]であるが、たとえば[[フクロウ目]]や[[ヨタカ目]]の多くの種は、[[夜行性]]ないし[[薄明薄暮性]](薄明の時間帯に活動する)であり、[[渉禽類]]には潮の干満にあわせて、昼夜に関わりなく採餌する種が多く存在する<ref>{{Cite journal |last=Robert |first=Michel |month=January |year=1989 |title=Conditions and significance of night feeding in shorebirds and other water birds in a tropical lagoon |journal=The Auk |volume=106 |issue=1 |pages=94–101 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Auk/v106n01/p0094-p0101.pdf |format=PDF |accessdate=2014-07-06}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 食餌と採餌 ===
| |
| − | [[ファイル:BirdBeaksA.svg|thumb|250px|upright|right|alt= ことなる形状と大きさのくちばしを持つ16種の鳥の頭部の図|くちばしの形状に見られる採餌への適応。]]
| |
| − | 鳥類の食餌は多彩であり、多くの場合、[[蜜]]や[[果実]]、[[植物]]、[[種子]]、[[腐肉|屍肉]]、他の鳥を含むさまざまな小動物などが含まれる<ref name=Gill_32>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、32頁</ref>。鳥には歯がないことから、その[[消化器系]]は、丸のみにした、[[咀嚼]]されていない食物を処理することに適応している<ref name=Gill_26-27・177-178>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、26-27頁、177-178頁</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類には、さまざまな食料において食物ないし餌を得るために、多くの方法を用いる「広食性(多食性)」(ゼネラリスト)と呼ばれるもののほか、特定の食料に時間と労力を集中させるか、単一の方法で食物を得る「狭食性(単食性)」(スペシャリスト)と呼ばれるものがいる<ref name = "Gill"/>。鳥類の採餌方法は種によって異なる。鳥類の多くは、[[昆虫]]や[[無脊椎動物]]、果実、または種子を採る ([[w:Gleaning (birds)|gleaning]])。なかには枝から急襲して昆虫を狩るものもある。[[害虫]]を狙うような種は、有益な「[[生物的防除]]」と見なされ、生物的防除プログラムにおいては、それらの生息が奨励されている<ref name="lwa001">{{cite web|url=http://lwa.gov.au/files/products/land-water-and-wool/pf061365/pf061365.pdf |format=PDF |title=Birds on New England wool properties - A woolgrower guide |publisher=Australian Government - Land and Water Australia |work=Land, Water & Wool Northern Tablelands Property Fact Sheet |author=N Reid |year=2006 |accessdate=2014-07-21}}</ref> 。[[ハチドリ|ハチドリ類]]、[[タイヨウチョウ科|タイヨウチョウ類]]、[[ヒインコ|ヒインコ類]]のような、とりわけ花蜜を採食するものは、特別に適応したブラシ状の[[舌]]を持ち、多くの場合くちばしの形状が[[共進化|共適応]]した花に適するようにデザインされている<ref>{{Cite journal |last=Paton |first=D. C. |date=1 April 1989|title=Bills and tongues of nectar-feeding birds: A review of morphology, function, and performance, with intercontinental comparisons |journal=Australian Journal of Ecology |volume=14 |issue=4 |pages=473–506 |doi=10.2307/1942194 |issn=00129615 |first2=. |last2=Baker |jstor=1942194}}</ref> 。[[キーウィ (鳥)|キーウィ]]や[[渉禽類]]は、その長いくちばしを[[探針]]として使い、無脊椎動物を探す。[[シギ科|シギ]]・[[チドリ科|チドリ類]]の間でくちばしの長さと採餌の方法に違いがあることによって、[[ニッチ|生態的地位]](生態的ニッチ)の分離が生じている<ref name=Gill_32-34>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、32-34頁</ref><ref>{{Cite journal |last=Baker |first=Myron Charles |date=1 April 1973|title=Niche Relationships Among Six Species of Shorebirds on Their Wintering and Breeding Ranges |journal=Ecological Monographs |volume=43 |issue=2 |pages=193–212 |doi=10.2307/1942194 |issn=00129615 |first2=. |last2=Baker |jstor=1942194}}</ref>。[[アビ科|アビ類]]、潜水ガモ類 ([[w:Diving duck|Diving duck]])、[[ペンギン|ペンギン類]]、[[ウミスズメ科|ウミスズメ類]]などは、水中で翼ないし足を推進器として使い、その獲物を追いかけるが<ref name = "Burger"/>、それに対して[[カツオドリ科|カツオドリ類]]や[[カワセミ科|カワセミ類]]、[[アジサシ亜科|アジサシ類]]のような飛翔型の捕食者は、獲物に狙いをつけて空中から水に飛び込む。[[フラミンゴ|フラミンゴ類]]、クジラドリ類 ([[w:Prion (bird)|Prion]]) のうちの3種、そして[[カモ|カモ類]]の一部は[[濾過摂食]]を行う<ref>{{Cite journal |last=Cherel |first=Yves |year=2002 |title=Food and feeding ecology of the sympatric thin-billed ''Pachyptila belcheri'' and Antarctic ''P. desolata'' prions at Iles Kerguelen, Southern Indian Ocean |journal=Marine Ecology Progress Series |volume=228 |pages=263–281 |doi=10.3354/meps228263 |last2=Bocher |first2=P |last3=De Broyer |first3=C |last4=Hobson |first4=KA}}</ref><ref>{{ Cite journal |last=Jenkin |first=Penelope M. |year=1957 |title=The Filter-Feeding and Food of Flamingoes (Phoenicopteri) |journal=Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences |volume=240 |issue=674 |pages=401–493 |doi=10.1098/rstb.1957.0004 |jstor=92549}}</ref>。[[雁|ガン類]]やカモ類は基本的に[[草食動物]]である。
| |
| − | | |
| − | [[グンカンドリ属|グンカンドリ類]]、[[カモメ科|カモメ類]]<ref>{{Cite journal |last=Miyazaki |first=Masamine |date=1 July 1996|title=Vegetation cover, kleptoparasitism by diurnal gulls and timing of arrival of nocturnal Rhinoceros Auklets |journal=The Auk |volume=113 |issue=3 |pages=698–702 |doi=10.2307/3677021 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Auk/v113n03/p0698-p0702.pdf |format=PDF |issn=09088857 |last2=Kuroki |last3=Niizuma |last4=Watanuki |first2=M. |first3=Y. |first4=Y. |jstor=3677021 |accessdate=2014-07-06}}</ref>、[[トウゾクカモメ科|トウゾクカモメ類]]<ref>{{Cite journal |last=Bélisle |first=Marc |date=1 August 1995|title=Predation and kleptoparasitism by migrating Parasitic Jaegers |journal=The Condor |volume=97 |issue=3 |pages=771–781 |doi=10.2307/1369185 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v097n03/p0771-p0781.pdf |format=PDF |issn=00105422 |author2=Giroux |accessdate=2014-07-06}}</ref>など一部の種は、[[労働寄生|盗み寄生]](ほかの鳥から食料になるものを奪い取ること)を行う。盗み寄生による食料はいずれの種においても、食料の主要な部分というよりは、むしろ狩猟による収穫を補うものであると考えられている。[[アオツラカツオドリ]]から餌を盗む[[オオグンカンドリ]]についての研究によれば、奪った餌の割合はかれらの食物のうち多くても40%、平均ではわずか5%と見積もられている<ref>{{Cite journal |last=Vickery |first=J. A. |date=1 May 1994|title=The Kleptoparasitic Interactions between Great Frigatebirds and Masked Boobies on Henderson Island, South Pacific |journal=The Condor |volume=96 |issue=2 |pages=331–40 |doi=10.2307/1369318 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v096n02/p0331-p0340.pdf |format=PDF |issn=00105422 |first2=. |last2=Brooke |jstor=1369318 |accessdate=2014-07-06}}</ref>。他の鳥類には[[腐肉食]]のものがある。なかにはコンドルのように、屍肉に特化したものもあり、また一方ではカモメや[[カラス]]、あるいは他の猛禽類のような日和見的に屍肉を利用するものもある<ref>{{Cite journal |last=Hiraldo |first=F.C. |year=1991 |title=Unspecialized exploitation of small carcasses by birds |journal=Bird Studies |volume=38 |issue=3 |pages=200–07 |doi=10.1080/00063659109477089 |last2=Blanco |first2=J. C. |last3=Bustamante |first3=J.}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 水の摂取 ===
| |
| − | 排泄方法と、[[汗腺]]の欠如によって、鳥類の水分に対する生理的要求は軽減されてはいるが、それでも多くの鳥にとって[[水]]は必要である<ref>{{Cite book|year=2005|url=http://irs.ub.rug.nl/ppn/287916626|isbn=90-367-2378-7|last=Engel|first=Sophia Barbara|title=Racing the wind: Water economy and energy expenditure in avian endurance flight|publisher=University of Groningen |accessdate=2014-07-06}}</ref>。ある種の砂漠の鳥は、その食物に含まれる水分だけで、必要とする水をすべて得ることができる。さらにかれらはこれ以外にも、体温の上昇を許容して蒸散冷却(浅速呼吸)による水分の損失を抑えるといった適応を行っていると考えられている<ref>{{Cite journal |first1=B.I. |last1=Tieleman |last2=Williams |first2=J.B |title=The Role of Hyperthermia in the Water Economy of Desert Birds|journal=Physiol. Biochem. Zool. |volume=72 |year=1999 |pages=87–100 |doi=10.1086/316640 |pmid=9882607 |month= January |issue=1 |issn=1522-2152 |url=http://www.biosci.ohio-state.edu/~patches/publication/TielemanWilliams1999_PBZ.pdf |format=PDF |accessdate=2014-07-06}}</ref>。[[海鳥]]は[[海水]]を飲むことができ、頭蓋内部に{{仮リンク|塩類腺|en|Salt gland}}を持っている。この塩類腺によって過剰な塩分を、[[鼻孔]]から排出する<ref>{{Cite journal |title=The Salt-Secreting Gland of Marine Birds|last=Schmidt-Nielsen|first=Knut|journal=Circulation|date=1 May 1960|volume=21|pages=955–967|url=http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/21/5/955|issue=5 |accessdate=2014-07-06}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | ほとんどの鳥は水を飲む際に、そのくちばしで水をすくい取り、そして水がのどを流れ落ちるように、頸を上にそらせる。一部の種、ことに乾燥した地域に生息する[[ハト科]]や[[カエデチョウ科]]、[[ネズミドリ科]]、[[ミフウズラ科]]、[[ノガン科]]などに属する種は、水をすする能力があり、その頭を後ろに傾ける必要がない<ref>{{Cite journal |first=Sara L. |last=Hallager |title=Drinking methods in two species of bustards |journal=Wilson Bull. |volume=106 |issue=4 |year=1994 |pages=763–764 |url=https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/wilson/v106n04/p0763-p0764.pdf |format=PDF |accessdate=2014-07-06}}</ref>。砂漠性の鳥の一部は水源に依存し、特に[[サケイ科]]の鳥は、毎日水たまりに集まってくることで有名である。営巣しているサケイ類や、チドリ科の多くの鳥は、その腹の羽毛に水を含ませて、雛に運ぶ<ref>{{Cite journal |title=Water Transport by Sandgrouse |first=Gordon L. |last=MacLean |journal=BioScience |volume=33 |issue=6 |date=1 June 1983 |pages=365–369 |doi=10.2307/1309104 |issn=00063568 |jstor=1309104}}</ref>。なかには、巣の雛に飲ませる水を、自分の[[素嚢]]に入れて運び、あるいは、餌と一緒に吐き戻す鳥もある。ハト科、フラミンゴ目やペンギン目の鳥は、[[素嚢乳]]と呼ばれる栄養分を含んだ液体を分泌して、これを雛に与えるような適応を行っている<ref>{{Cite journal |author=Eraud C |coauthors=Dorie A; Jacquet A & Faivre B |year=2008 |title=The crop milk: a potential new route for carotenoid-mediated parental effects |journal=Journal of Avian Biology |volume=39 |pages=247–251 |doi= 10.1111/j.0908-8857.2008.04053.x|issue=2}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 渡り ===
| |
| − | {{Main|渡り鳥}}
| |
| − | たくさんの種の鳥類が、季節ごとの気温の地域差を利用するために渡りをおこない、これによって食料供給や繁殖地の確保の最適化を図っている。これらの渡りの行動は、それぞれのグループによって異なっている。通常、天候条件とともに日長の変化をきっかけとして、多くの陸鳥、[[海鳥]]、[[渉禽類]]および[[水鳥]]が毎年、長距離の渡りに乗り出して行く。これらの鳥類を特徴づけているのは、かれらが繁殖期を[[温帯|温暖な地域]]、ないしは[[北極]]または[[南極]]の極地方で過ごし、そうでない時期を[[熱帯]]地方か、あるいは反対の半球で過ごすことである。渡りに先立って、鳥たちは[[体脂肪]]と栄養の蓄積を大幅に増やし、また一部の体組織の大きさを縮小させる<ref name = "Battley"/><ref name = "Klaassen">{{Cite journal |last=Klaassen |first=Marc |coauthors= |date=1 January 1996 |title=Metabolic constraints on long-distance migration in birds |journal=Journal of Experimental Biology |volume=199 |issue=1 |pages=57–64 |pmid=9317335 |url=http://jeb.biologists.org/cgi/reprint/199/1/57 |issn=0022-0949 |accessdate=2014-07-07}}</ref>。渡りは、特に食料補給なしに砂漠や大洋を横断する必要がある鳥たちにとって、多くのエネルギーを必要とする。陸棲の小鳥はおよそ{{convert|2500|km|mi|-2|abbr=on}} 前後の飛翔持続距離を持ち、シギ・チドリ類は{{convert|4000|km|mi|-2|abbr=on}}を飛ぶことができるとされ<ref name=Gill_291-293>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、291-293頁</ref>、[[オオソリハシシギ]]は{{convert|11000|km|mi|-2|abbr=on}}の距離を飛び続ける能力がある<ref name=Gill_285>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、285頁</ref><ref name=Higuchi2016_22・112-113>[[#樋口2016|樋口 (2016)]]、22頁、112-113頁</ref><ref>{{Cite web|title=The Bar-tailed Godwit undertakes one of the avian world's most extraordinary migratory journeys |url=http://www.birdlife.org/datazone/sowb/casestudy/22 |year=2010 |publisher=[[BirdLife International]] |accessdate=2014-07-07}}</ref>。[[海鳥]]も長距離の渡りを行い、なかでも最も長距離の周期的な渡りを行うのが[[ハイイロミズナギドリ]]である。かれらは[[ニュージーランド]]や[[チリ]]で営巣し、北半球の夏を、[[日本]]や[[アラスカ]]、[[カリフォルニア]]沖の北太平洋で、餌を採って過ごす。この季節的な周回移動は、総距離 {{convert|64000|km|mi|-2|abbr=on}} にもおよぶ<ref name=Higuchi2016_113-114>[[#樋口2016|樋口 (2016)]]、113-114頁</ref><ref>{{Cite journal |last=Shaffer |first=Scott A. |year=2006 |title=Migratory shearwaters integrate oceanic resources across the Pacific Ocean in an endless summer |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences |volume=103 |issue=34 |pages=12799–12802 |doi=10.1073/pnas.0603715103 |pmid=16908846 |month= August|issn=0027-8424 |url=http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16908846 |last2=Tremblay |first2=Y |last3=Weimerskirch |first3=H |last4=Scott |first4=D |last5=Thompson |first5=DR |last6=Sagar |first6=PM |last7=Moller |first7=H |last8=Taylor |first8=GA |last9=Foley |first9=DG |pmc=1568927 |accessdate=2014-07-07}}</ref>。このほかの海鳥では、繁殖期が過ぎると分散して広い範囲を移動するが、一定の渡りのルートを持たない。[[南極海]]で営巣するアホウドリは、繁殖期と繁殖期の間に、しばしば極周回の移動を行っている<ref>{{Cite journal |last=Croxall |first=John P. |year=2005 |title=Global Circumnavigations: Tracking year-round ranges of nonbreeding Albatrosses |journal=Science |volume=307 |issue=5707 |pages=249–50 |doi=10.1126/science.1106042 |pmid=15653503 |month= January|issn=0036-8075 |last2=Silk |first2=JR |last3=Phillips |first3=RA |last4=Afanasyev |first4=V |last5=Briggs |first5=DR}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | [[ファイル:Bar-tailed Godwit migration.jpg|alt=ニュージーランドから韓国に至る、鳥の飛行経路を示す複数の着色した線が描かれている太平洋の地図|thumb|left|人工衛星によって追跡された、[[ニュージーランド]]から北へ向かう[[ハイイロミズナギドリ]]の渡りの経路。かれらは海鳥のなかで最長の{{convert|10200|km|mi|-2|abbr=on}}にもおよぶ、ノンストップの渡りを行う種として知られている。]]
| |
| − | 悪天候を避けたり、食料を得たりするのに必要なだけの、より短い移動を行う鳥もいる。北方の[[アトリ科|アトリ類]]のような大発生する種は、そのようなグループのひとつであり、ある年にはある場所でごく普通に見られたものが、次の年には全くいなくなったりする。この種の渡りは、通常、食料入手の容易さに関連している<ref>{{Cite journal |last=Wilson |first=W. Herbert, Jr. |year=1999 |title=Bird feeding and irruptions of northern finches:are migrations short stopped? |journal=North America Bird Bander |volume=24 |issue=4|pages=113–21 |url= https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/nabb/v024n04/p0113-p0121.pdf |format=PDF |accessdate=2014-07-07}}</ref>。高緯度地方にいた個体が、同種の鳥がすでにいる分布域に移動するように、分布域内でのさらに短距離の渡りをする種もいる。そしてほかのものは、個体群の一部分だけ(普通、雌と劣位の雄たち)が移動する部分的な渡り (partial migration) を行う<ref>{{Cite journal |last=Nilsson |first=Anna L. K. |year=2006 |title=Do partial and regular migrants differ in their responses to weather? |journal=The Auk |volume=123 |issue=2 |pages=537–547 |url=http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3793/is_200604/ai_n16410121|doi=10.1642/0004-8038(2006)123[537:DPARMD]2.0.CO;2 |last2=Alerstam |first2=Thomas |last3=Nilsson |first3=Jan-Åke|issn=0004-8038}}</ref>。部分的な渡りは、地域によって、鳥類の渡り行動の大きなパーセンテージを占めることがある。オーストラリアでの調査によれば、非スズメ目の鳥でその44%が、またスズメ目の鳥でその32%が、部分的な渡りを行っていることがわかっている<ref>{{Cite journal |last=Chan |first=Ken |year=2001 |title=Partial migration in Australian landbirds: a review |journal=[[w:Emu (journal)|Emu]] |volume=101 |issue=4 |pages=281–92 |doi=10.1071/MU00034 |url=http://www.publish.csiro.au/paper/MU00034.htm |accessdate=2014-07-07}}</ref>。高さの移動 (Altitudinal migration) は、短距離の渡りのひとつの形態で、繁殖期を高地で過ごし、準最適の条件下では、より高度の低い地域に移動するような鳥に見られる。この行動のきっかけは気温の変化であることが最も多く、通常の縄張りが、食料不足によって生息に適さなくなるときに起こるのが普通である<ref>{{Cite journal |last=Rabenold |first=Kerry N. |year=1985 |title=Variation in Altitudinal Migration, Winter Segregation, and Site Tenacity in two subspecies of Dark-eyed Juncos in the southern Appalachians |journal=The Auk|volume=102 |issue=4 |pages=805–19 |url=https://84a69b9b8cf67b1fcf87220d0dabdda34414436b-www.googledrive.com/host/0B0PLtJjhTxnkZDAzOGQxY2EtOTIzOS00ZjlkLWJhYmMtYWYzY2QwYmQ2ZjFi/Documents/LEFHE%20Studies%20Real%20Time%20(C.%20Avon)/Ornithological%20Monographs%20and%20Reprints/MAHN-84%20Archives%20Ornithological%20reprints%20(2001-3000)/MAHN-84%20Archives%20Ornithological%20Reprints%202608.pdf |format=PDF |accessdate=2014-07-07}}</ref>。また一部の種は放浪性である場合もあり、決まった縄張りを持たず、気候や食料の得やすさに応じて移動する。[[インコ]]科の大部分は渡りもしないが定住性でもなく、分散的か、突発的か、放浪性か、あるいは小規模で不規則な渡りをするか、そのいずれかとみなされている<ref>{{Cite book|last=Collar |first=Nigel J. |year=1997|chapter=Family Psittacidae (Parrots)|title=[[w:Handbook of the Birds of the World|Handbook of the Birds of the World]], Volume 4: Sandgrouse to Cuckoos |editor=Josep del Hoyo, Andrew Elliott and Jordi Sargatal (eds.) |location=Barcelona |publisher=Lynx Edicions |isbn=84-87334-22-9|pages=}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類が、膨大な距離を超えて、正確な位置に戻ってくる能力を持っていることは以前から知られていた。1950年代に行われた実験では、[[ボストン]]で放された[[マンクスミズナギドリ]]は、13日後に{{convert|5150|km|mi|-2|abbr=on}} の距離を越えて、[[ウェールズ]]州{{仮リンク|スコーマー島|en|Skomer}}にあったもとの集団繁殖地(コロニー)に帰還した<ref>{{Cite journal |last=Matthews |first=G. V. T. |date=1 September 1953|title=Navigation in the Manx Shearwater |journal=Journal of Experimental Biology |volume=30 |issue=2 |pages=370–396 |url=http://jeb.biologists.org/cgi/reprint/30/3/370}}</ref>。鳥は渡りの間、さまざまな方法を使って[[航法|航行]]している。[[昼行性]]の渡り鳥の場合、日中の航行には[[太陽]]が用いられ、夜間は恒星がコンパスとして使用される。太陽を用いる鳥は、日中の太陽の移動を、[[体内時計]]を利用して補正している<ref name=Gill_300>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、300頁</ref>。恒星によるコンパスでは、その方向は、[[北極星]]を取り囲む[[星座]]の位置に依存している<ref>{{Cite journal |last=Mouritsen |first=Henrik |date=15 November 2001|title=Migrating songbirds tested in computer-controlled Emlen funnels use stellar cues for a time-independent compass |journal=Journal of Experimental Biology |volume=204 |issue=8 |pages=3855–3865 |pmid=11807103 |url=http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/204/22/3855 |issn=0022-0949 |author2=L |accessdate=2014-07-07}}</ref>。ある種の鳥たちはこれらの航法を、特殊な[[光受容体]]による地球の[[地磁気]]を検知する能力によってバックアップしている<ref>{{Cite journal |last=Deutschlander |first=Mark E. |date=15 April 1999|title=The case for light-dependent magnetic orientation in animals |journal=Journal of Experimental Biology |volume=202 |issue=8 |pages=891–908 |pmid= 10085262 |url=http://jeb.biologists.org/cgi/reprint/202/8/891 |issn=0022-0949 |author2=P |author3=B |accessdate=2014-07-07}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === コミュニケーション ===
| |
| − | {{See also|{{仮リンク|鳥類の鳴き声|en|Bird vocalization}}}}
| |
| − | [[ファイル:Stavenn Eurypiga helias 00.jpg|thumb|alt= 中央部に大きな斑点を持つ翼をそれぞれ左右いっぱいに広げている、大型で褐色の模様の陸鳥| right|[[ジャノメドリ]]の驚くべきディスプレイ。大型の捕食者に擬態している。]]
| |
| − | 鳥類は、基本的に視覚的信号と聴覚信号を使って[[動物のコミュニケーション|コミュニケーション]]を行う。これらの信号は、異種の間(種間)の場合も、同一種内(種内)の場合もある。
| |
| − | | |
| − | 鳥類は、ときには社会的な優位性を判断したり、主張するために羽衣を使用することがあり<ref>{{Cite journal |last=Möller |first=Anders Pape |year=1988 |title=Badge size in the house sparrow ''Passer domesticus''|journal=[[w:Behavioral Ecology and Sociobiology|Behavioral Ecology and Sociobiology]] |volume=22 |issue=5 |pages=373–78}}</ref>、また、[[性淘汰]]の起こった種のなかでは、繁殖可能な状態にあることを示すために使われることもある。あるいはまた、[[ジャノメドリ]]に見られるように、親鳥が幼い雛を守るため、大型捕食者の[[擬態]]をして[[タカ目|タカ類]]などを脅かし追い払うために羽衣が使われることもある<ref>{{Cite journal |last1=Thomas |first1=Betsy Trent |last2=Strahl |first2=Stuart D. |date=1 August 1990 |title=Nesting Behavior of Sunbitterns (''Eurypyga helias'') in Venezuela |journal=The Condor |volume=92 |issue=3 |pages=576–81 |doi=10.2307/1368675 |url= http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/condor/v092n03/p0576-p0581.pdf |format=PDF |issn=00105422 |accessdate=2014-07-07}}</ref>。羽衣のバリエーションはまた、特に異種間において、種の識別を可能にする。鳥類相互の視覚的コミュニケーションには、羽繕いや羽毛の位置の調整(整羽)、突つき、あるいは他のさまざまな行動のような、信号としてではない動作から発展したと考えられる、儀式化されたディスプレイが含まれる。これらのディスプレイは、攻撃ないし服従の信号である場合もあるし、また{{仮リンク|つがい|en|Breeding pair}}(ペア)関係の形成に寄与する場合もある<ref name = "Gill"/>。最も精巧なディスプレイは、求愛の際に行われる。このいわゆる“ダンス”は多くの場合、なし得るいくつもの動作を構成要素とする複雑な組み合わせによって構成されており<ref>{{Cite journal |last=Pickering |first=S. P. C. |year=2001 |title=Courtship behaviour of the Wandering Albatross ''Diomedea exulans'' at Bird Island, South Georgia |journal=Marine Ornithology |volume=29 |issue=1 |pages=29–37 |url=http://www.marineornithology.org/PDF/29_1/29_1_6.pdf |format=PDF |accessdate=2014-07-07}}</ref>、雄の繁殖の成功は、そのようなディスプレイの出来栄えに左右されることもある<ref>{{Cite journal |last=Pruett-Jones |first=S. G. |date=1 May 1990 |title=Sexual Selection Through Female Choice in Lawes' Parotia, A Lek-Mating Bird of Paradise |journal=[[w:Evolution (journal)|Evolution]] |volume=44 |issue=3 |pages=486–501 |doi=10.2307/2409431 |issn=00143820 |author2=Pruett-Jones}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | {{Listen|filename=Troglodytes aedon - House Wren - XC79974.ogg|title=イエミソサザイ|description=[[新北区]]([[北アメリカ]])で一般的な鳴禽である、[[イエミソサザイ]]のさえずり}}
| |
| − | {{Listen|filename=Troglodytes_troglodytes_song.ogg|title=ミソサザイ|description=[[旧北区]]に広く分布する、[[ミソサザイ]]の特徴的なさえずり}}
| |
| − | [[鳴管]]によって発せられる鳥類の{{仮リンク|鳥類の鳴き声|en|Bird vocalization|label=地鳴きやさえずり}}は、鳥類が[[音]]によってコミュニケーションを行う際の主要な手段である。このコミュニケーションは、非常に複雑になる場合がある。なかには鳴管の両側をそれぞれ独立して機能させることができる種もあり、これによって2つの異なるさえずりを同時に発声することを可能にしている<ref name = "Suthers"/>。
| |
| − | | |
| − | 鳴き声はさまざまな目的に使用される。たとえばつがい相手の誘引や<ref name=Gill_228>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、228頁</ref>、可能性のあるつがい相手の値踏み<ref>{{Cite journal |last=Genevois |first=F. |year=1994|last2=Bretagnolle|first2=V. |title=Male Blue Petrels reveal their body mass when calling |journal=Ethology Ecology and Evolution |volume=6 |issue=3 |pages=377–83 |doi=10.1080/08927014.1994.9522988 |url=http://ejour-fup.unifi.it/index.php/eee/article/view/667/613}}</ref>、つがいの形成、縄張りの主張と維持<ref name=Gill_228 />、他の個体の識別(たとえば親鳥が集団繁殖地(コロニー)で雛を探すとき、また繁殖期の初めにつがい相手が再会するとき)<ref>{{Cite journal |last=Jouventin |first=Pierre |month= June|year=1999 |title=Finding a parent in a king penguin colony: the acoustic system of individual recognition |journal=Animal Behaviour |volume=57 |issue=6 |pages=1175–83 |doi=10.1006/anbe.1999.1086 |pmid=10373249 |issn=0003-3472 |last2=Aubin |first2=T |last3=Lengagne |first3=T}}</ref> 、あるいは、捕食者らしきものの接近をほかの鳥へ警告したり、またときには脅威の性質に関する一定の情報である場合もある<ref>{{Cite journal |last=Templeton |first=Christopher N. |year=2005 |title=Allometry of Alarm Calls: Black-Capped Chickadees Encode Information About Predator Size |journal=Science |volume=308 |issue=5730 |pages=1934–37 |doi=10.1126/science.1108841 |pmid=15976305 |month= June|issn=0036-8075 |last2=Greene |first2=E |last3=Davis |first3=K}}</ref><ref name=Gill_228-230>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、228-230頁</ref>。また一部の鳥類は、機械的に発生させた音を聴覚的コミュニケーションに使用する。[[オオジシギ]]や<ref>{{Cite book|和書 |editor=高野伸二 |year=1981 |title=カラー写真による 日本産鳥類図鑑 |publisher=[[学校法人東海大学出版会|東海大学出版会]] |page=281}}</ref>、[[ニュージーランド]]産のジシギ ''[[w:Coenocorypha|Coenocorypha]]'' などは、その羽毛に空気を通して振動させる<ref name = "Miskelly">{{Cite journal |last=Miskelly |first=C. M. |coauthors= |month=July |year=1987 |title=The identity of the hakawai |journal=Notornis |volume=34 |issue=2 |pages=95–116 |url= http://extinct-website.com/pdf/Notornis_34_2_95_116.pdf |format=PDF |accessdate=2014-07-07}}</ref>。この尾羽で音を発するディスプレイ・フライトは、ほとんどのジシギ類で見られる<ref name = "Miskelly"/><ref>{{Cite journal |和書|author=茂田良光 |title=ジシギ類ってどんな鳥 |date=2000-05 |publisher=文一総合出版 |journal=Birder |volume=14 |number=5 |pages=26-31}}</ref>。また[[キツツキ科|キツツキ類]]は縄張りでドラミングを行い<ref name = "Attenborough"/>、[[ヤシオウム]]はドラミングのために道具を使う<ref>{{Cite journal |last=Murphy |first=Stephen |year=2003 |title=The breeding biology of palm cockatoos (''Probosciger aterrimus''): a case of a slow life history |journal=[[w:Journal of Zoology]] |volume=261 |issue=4 |pages=327–39 |doi=10.1017/S0952836903004175 |last2=Legge |first2=Sarah |last3=Heinsohn |first3=Robert}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | [[ファイル:Red-billed quelea flocking at waterhole.jpg|thumb|left|alt= 遠くから眺めた小さな鳥の巨大な群れ。鳥たちがしみのように見える。|[[コウヨウチョウ]]は最も個体数の多い種で<ref name="flycatcher">{{Cite book|last=Sekercioglu |first=Cagan Hakki |year=2006 |chapter=Foreword |title=[[w:Handbook of the Birds of the World|Handbook of the Birds of the World]], Volume 11: Old World Flycatchers to Old World Warblers|editor=Josep del Hoyo, Andrew Elliott and David Christie (eds.) |location=Barcelona |publisher=Lynx Edicions |isbn=84-96553-06-X|page=48}}</ref>、ときには数万羽を越える巨大な群れを形成する。]]
| |
| − | | |
| − | === 群れの形成とその他の集合体 ===
| |
| − | ある鳥類は、縄張りでの生活や、小さな家族群での生活を基本とするが、そうではない鳥は大きな群れ ([[w:Flock (birds)|Flock]]) を形成することがある。群れをつくることの大きな利点は、数が多いことによる安全性 ([[w:Safety in numbers|Safety in numbers]]) であり、そして採餌効率の向上である<ref name = "Gill"/>。捕食者に対する防御は、樹林のような閉じた生息地ではことのほか重要である。そこでは待ち伏せ型の捕食者 ([[w:Ambush predator|Ambush predator]]) が一般的であり、複数の目による監視によって有効な早期警戒態勢を準備することができる。このことから、通常は多くの種の少数の個体から構成される数多くの混群 ([[w:Mixed-species foraging flock|Mixed-species flock]]) の形成に繋がっている。こういった群れは、群集による安全性をもたらすが、資源を得るための潜在的な競争を増やす<ref>{{Cite journal |last=Terborgh |first=John |year=2005 |title=Mixed flocks and polyspecific associations: Costs and benefits of mixed groups to birds and monkeys |journal=American Journal of Primatology |volume=21 |issue=2|pages=87–100 |doi=10.1002/ajp.1350210203}}</ref>。群れを形成することの代償には、社会的地位が低い鳥に対する、より優位な鳥によるいじめや、特定の条件下での採餌効率の低下などがある<ref>{{Cite journal |last=Hutto |first=Richard L. |date=1 January 1988|title=Foraging Behavior Patterns Suggest a Possible Cost Associated with Participation in Mixed-Species Bird Flocks |journal=[[w:Oikos (journal)|Oikos]] |volume=51 |issue=1 |pages=79–83 |doi=10.2307/3565809 |issn=00301299 |jstor=3565809}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類は、ときに鳥類以外の種と関連をなすこともある。上空から急降下して潜水し捕食するタイプの海鳥は、魚群を海面に押し上げてくれる[[イルカ]]や[[ツナ|マグロ]]の群れに加わる<ref name = "AU">{{Cite journal |last=Au |first=David W. K. |date=1 August 1986|title=Seabird interactions with Dolphins and Tuna in the Eastern Tropical Pacific |journal=The Condor |volume=88 |issue=3 |pages=304–17 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v088n03/p0304-p0317.pdf |doi=10.2307/1368877|format=PDF |issn=00105422 |author2=Pitman}}</ref> 。[[サイチョウ科|サイチョウ類]]は、{{仮リンク|コビトマングース|en|Common Dwarf Mongoose}}と[[相利共生]]的な関係にある。かれらは一緒に餌を探し、[[猛禽]]や、そのほかの捕食者の接近を互いに警告しあう<ref>{{Cite journal |last=Anne |first=O. |date=June 1983 |title=Dwarf mongoose and hornbill mutualism in the Taru desert, Kenya |journal=Behavioral Ecology and Sociobiology |volume=12 |issue=3 |pages=181–90 |doi=10.1007/BF00290770 |last2=Rasa |first2=E.}}</ref>。
| |
| − | {{-}}
| |
| − | | |
| − | === 睡眠とねぐら ===<!--ねぐら redirects here-->
| |
| − | [[ファイル:Caribbean Flamingo2 (Phoenicopterus ruber) (0424) - Relic38.jpg|thumb|alt= 灰色の足をしたピンク色のフラミンゴが、長い頸を体に押し付けて、頭を翼の下に押し込んでいる。|多くの鳥類は、この[[ベニイロフラミンゴ]]のように、眠るときには頭部を背に押し込む。]]
| |
| − | | |
| − | 鳥類の一日における活動時の高い代謝率は、これ以外の時間の休息によって補われている。眠る鳥は、警戒睡眠 (vigilant sleep) として知られるタイプの睡眠をしばしば取る。このタイプの睡眠では、素早く目を開く「一瞥」 (peeks) がその間に組み入れられ、これによってかれらは異常に対して鋭敏になり、脅威から素早く逃れられる<ref>{{Cite journal |last=Gauthier-Clerc |first=Michael |date=May 2000 |title=Sleep-Vigilance Trade-off in Gadwall during the Winter Period |journal=The Condor |volume=102 |issue=2 |pages=307–13 |url=https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/condor/v102n02/p0307-p0313.pdf |format=PDF |doi=10.1650/0010-5422(2000)102[0307:SVTOIG]2.0.CO;2 |last2=Tamisier |first2=Alain |last3=Cézilly |first3=Frank|issn=0010-5422 |accessdate=2014-07-08}}</ref>。[[アマツバメ科|アマツバメ類]]は、飛翔中に睡眠を取ることができると考えられており<ref name=Higuchi2016_21-22>[[#樋口2016|樋口 (2016)]]、21-22頁</ref>、レーダー観測では、その飛翔中の休息の際、かれらは風上に向かうように自分の方向を定めることを示している<ref>{{Cite journal |journal=The Journal of Experimental Biology|volume=205|pages=905–910|date=1 April 2002|title=Harmonic oscillatory orientation relative to the wind in nocturnal roosting flights of the swift ''Apus apus''|first=Johan|last=Bäckman|url=http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/205/7/905|pmid=11916987|issue=7|issn=0022-0949|author2=A |accessdate=2014-07-08}}</ref>。それは、おそらくは飛翔中であっても可能であるような、ある種の睡眠が存在する可能性を示唆している<ref>{{Cite journal |last=Rattenborg |first=Niels C. |year=2006 |month=September |title=Do birds sleep in flight? |journal=Die Naturwissenschaften |volume=93 |issue=9 |pages=413–425 |doi=10.1007/s00114-006-0120-3 |pmid=16688436 |issn=0028-1042}}</ref>。また、一部の鳥類では、同時に脳の一方の半球 ([[w:Cerebral hemisphere|hemisphere]]) が、[[徐波睡眠]] ([[w:Slow-wave sleep|SWS]]) に入る能力が証明されている。鳥類はこの能力を、群れの外側に対し、その位置に応じて働かせる傾向がある。これは、眠っている脳半球の反対側の目が群れの外側を見張ることによって、[[捕食]]者に対する警戒を可能にする。こういった適応はまた、[[海獣|海棲哺乳類]]においても知られている<ref>{{Cite journal |last=Milius |first=S. |date=6 February 1999|title=Half-asleep birds choose which half dozes |journal=Science News Online |volume=155 |issue= 6|page=86 |url=http://findarticles.com/p/articles/mi_m1200/is_6_155/ai_53965042 |doi=10.2307/4011301 |issn=00368423 |jstor=4011301 |archiveurl=http://archive.is/QfKO|archivedate=2012-05-29}}</ref>。鳥が集団でねぐらに集まることは一般的であり、それは[[体温#体温調節|体熱の損失]]を抑え、捕食者に関連する危険を減らすためである<ref>{{Cite journal |last=Beauchamp |first=Guy |year=1999 |title=The evolution of communal roosting in birds: origin and secondary losses |journal=Behavioural Ecology |volume=10 |issue=6 |pages=675–87 |url=http://beheco.oxfordjournals.org/cgi/content/full/10/6/675 |doi=10.1093/beheco/10.6.675 |accessdate=2014-07-08}}</ref> 。ねぐらの場所は、多くの場合、体温調節や安全性を考慮して選択される<ref>{{Cite journal |last=Buttemer |first=William A.|year=1985 |title=Energy relations of winter roost-site utilization by American goldfinches (''Carduelis tristis'') |journal=[[w:Oecologia]] |volume=68 |issue=1 |pages=126–32 |url=http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/47760/1/442_2004_Article_BF00379484.pdf |format=PDF |doi=10.1007/BF00379484 |accessdate=2014-07-08}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 多くの鳥類は、睡眠の際にその頭部を背に折り曲げて、くちばしを背の羽毛のなかに差し込むが、そのほか胸の羽毛のなかにくちばしを納める鳥もある。多くの鳥類は一本脚で休み、なかには特に寒冷な気候において、両脚を羽毛のなかに引き込むものもある。木に止まる[[スズメ目]]の鳥には、腱のロック機構が備わっており、睡眠中に止まり木の上に留まるのに役立っている。[[ウズラ類]]や[[キジ亜科 (Sibley)|キジ類]]といった多くの陸禽が木に止まる。[[インコ|インコ類]]のうち、サトウチョウ属 (''[[w:Loriculus|Loriculus]]'') などいくつかに属する鳥は、逆さまにぶら下がって休む<ref>{{Cite journal |last=Buckley |first=F. G. |date=1 January 1968|title=Upside-down Resting by Young Green-Rumped Parrotlets (''Forpus passerinus'') |journal=The Condor |volume=70 |issue=1 |page=89 |url=https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/condor/v070n01/p0089-p0089.pdf |format=PDF |doi=10.2307/1366517 |issn=00105422 |author2=Buckley |accessdate=2014-07-11}}</ref>。[[ハチドリ]]のなかには、夜間、代謝率の低下を伴う{{仮リンク|休眠状態|en|Torpor}}になるものがある<ref>{{Cite journal |last=Carpenter |first=F. Lynn |month= February |year=1974 |title=Torpor in an Andean Hummingbird: Its Ecological Significance |journal=Science |volume=183 |issue=4124 |pages=545–547 |doi=10.1126/science.183.4124.545 |pmid=17773043 |issn=0036-8075}}</ref>。この[[生理学|生理学的]][[適応]]は、[[ズクヨタカ科|ズクヨタカ類]]や[[ヨタカ科|ヨタカ類]]、[[モリツバメ科|モリツバメ類]]など、100種近いほかの鳥類にも見られる。ただ1種、{{仮リンク|プアーウィルヨタカ|en|Common Poorwill}}は、[[冬眠]]状態に入ることさえある<ref>{{Cite journal |last=McKechnie |first=Andrew E. |year=2007 |title=Torpor in an African caprimulgid, the freckled nightjar ''Caprimulgus tristigma'' |journal=Journal of Avian Biology |volume=38 |issue=3 |pages=261–66 |doi=10.1111/j.2007.0908-8857.04116.x |last2=Ashdown |first2=Robert A. M. |last3=Christian |first3=Murray B. |last4=Brigham |first4=R. Mark}}</ref>。鳥類は汗腺を持たないが、日陰に移動したり、水のなかにいたり、あえぎ呼吸(パンティング、panting)をしたり、表面積を大きくしたり、喉をはためかせたりしてその体を冷却し、あるいはまた、[[w:Urohidrosis|Urohidrosis]](冷却のメカニズムとして自分の脚の鱗の部分に糞をする行動)のような特別な行動をすることによって、自身を冷却することがある。
| |
| − | | |
| − | === 繁殖 ===
| |
| − | {{see also|{{仮リンク|海鳥の繁殖行動|en|Seabird breeding behavior}}|{{仮リンク|鳥類の性的選択|en|Sexual selection in birds}}}}
| |
| − | ==== 社会システム ====
| |
| − | [[ファイル:Raggiana Bird-of-Paradise wild 5.jpg|thumb|alt= 緑色の顔、黒い胸そしてピンク色の下半身をした鳥が、上を向いている。精巧な長い羽が、その翼と尾にある。|right|[[アカカザリフウチョウ]]の雄は、他のフウチョウ属の鳥と同様、精巧な繁殖羽を、雌に自分を印象づけるために使う<ref>{{Cite journal |last=Frith |first=C.B |title=Displays of Count Raggi's Bird-of-Paradise ''Paradisaea raggiana'' and congeneric species |journal=Emu |volume=81 |issue=4 |pages=193–201 |year=1981 |doi=10.1071/MU9810193 |url=http://www.publish.csiro.au/paper/MU9810193.htm |accessdate=2014-07-12}}</ref>。]]
| |
| − | 鳥類の種の95%は、社会的に一夫一婦である。これらの種のつがいは、最低でもその繁殖期の間か、場合によっては数年ないし配偶者が死ぬまで続く<ref>{{Cite journal |last=Freed|first=Leonard A.|year=1987|title=The Long-Term Pair Bond of Tropical House Wrens: Advantage or Constraint?|journal=[[w:The American Naturalist|The American Naturalist]]|volume=130|issue=4|pages=507–25|doi=10.1086/284728}}</ref>。一夫一婦は、雄による世話および[[親の投資|両親による子育て]]が可能となり、雌が育雛(いくすう)の成功のために雄の手助けが必要である種にとってきわめて重要である<ref>{{Cite journal |last=Gowaty|first=Patricia A.|title=Male Parental Care and Apparent Monogamy among Eastern Bluebirds (''Sialia sialis'')|journal=[[w:The American Naturalist|The American Naturalist]]|volume=121|issue=2|pages=149–60|year=1983|doi=10.1086/284047}}</ref>。多くの社会的に一夫一婦である種において、配偶者以外との交尾(婚外関係)は一般的である<ref>{{Cite journal |last=Westneat|first=David F.|year=2003|title=Extra-pair paternity in birds: Causes, correlates, and conflict|url=http://arjournals.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132439 |doi=10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132439|journal=[[w:Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics|Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics]]|volume=34|pages=365–96|last2=Stewart|first2=Ian R.K.}}</ref>。雌にとって、婚外交尾による利点は、その子により良い遺伝子を得られることや、配偶者による不妊の可能性に対して保険をかけることなどがある<ref>{{Cite journal |last=Sheldon|first=B|year=1994|title=Male Phenotype, Fertility, and the Pursuit of Extra-Pair Copulations by Female Birds|journal=Proceedings: Biological Sciences|volume=257|issue=1348|pages=25–30|doi=10.1098/rspb.1994.0089}}</ref>。婚外交尾に関わった種の雄は、かれらの作った子の親子関係を裏付けるために、その相手をしっかりと保護する<ref>{{Cite journal |last=Wei|first=G|year=2005|title=Copulations and mate guarding of the Chinese Egret |doi=10.1675/1524-4695(2005)28[527:CAMGOT]2.0.CO;2|journal=Waterbirds|volume=28|issue=4|pages=527–30|last2=Zuo-Hua|first2=Yin|last3=Fu-Min|first3=Lei|issn=1524-4695}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | これ以外の[[配偶システム]]としては、[[一夫多妻制|一夫多妻]]、[[一妻多夫制|一妻多夫]]、[[複婚]]、それに[[乱婚]](多夫多妻)もある<ref name=Gill_368>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、368頁</ref><ref name=Yamagishi2002_111・118-119>[[#山岸2002|山岸 (2002)]]、111頁、118-119頁</ref>。複婚の一種である一夫多妻の配偶システムは、雌が雄の手助けなしで哺育を行うことができる場合に生ずる<ref name=Gill_370-372>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、370-372頁</ref><ref name=Yamagishi2002_109-112・121-122>[[#山岸2002|山岸 (2002)]]、109-112頁、121-122頁</ref>。なかには環境に応じてさまざまな配偶システムを採用する種もある。
| |
| − | | |
| − | 繁殖には、通常何らかの形の求愛ディスプレイを伴い、一般的には雄によって演じられる<ref>{{Cite book|last=Short|first=Lester L.|year=1993|title=Birds of the World and their Behavior|publisher=Henry Holt and Co|location=New York|isbn=0-8050-1952-9}}</ref>。ほとんどのディスプレイは比較的単純であり、ある種の{{仮リンク|鳥類の鳴き声|en|Bird vocalization|label=さえずり}}を伴う。しかしながら、なかにはきわめて精巧なディスプレイもある。種によっては、翼や尾を鳴らす、ダンスや曲技飛翔、あるいは共同の[[配偶システム#レック型一夫多妻|レッキング]] ([[w:Lek mating|lekking]]) などがある。通常、雌がパートナーの選択を行うが<ref>{{Cite book|last=Burton|first=R|year=1985|title=Bird Behavior|publisher=Alfred A. Knopf, Inc|isbn=0-394-53957-5}}</ref>、しかし、一妻多夫の[[ヒレアシシギ属|ヒレアシシギ類]]では、これが逆転し、羽衣の地味な雄が鮮やかな色の雌を選択する<ref>{{Cite journal |last=Schamel |first=D |year=2004 |title=Mate guarding, copulation strategies and paternity in the sex-role reversed, socially polyandrous red-necked phalarope ''Phalaropus lobatus''|journal=Behaviour Ecology and Sociobiology |volume=57 |issue=2 |pages=110–118 |url=http://www.springerlink.com/index/8BE48GKGYF2Q40LT.pdf |doi=10.1007/s00265-004-0825-2 |last2=Tracy |first2=Diane M. |last3=Lank |first3=David B. |last4=Westneat |first4=David F. |accessdate=2014-07-12}}</ref>。求愛給餌 ([[w:Nuptial gift|courtship feeding]])、くちばし触れ合い ([[w:Beak#Billing|billing]])、互いの羽繕いなどは、通常、鳥がつがいになり交尾したのち、配偶者間で行われている<ref name = "Attenborough"/>。
| |
| − | | |
| − | [[動物の同性愛|同性愛]]の行動は、数多くの鳥類の種の雄または雌で観察されており、これには交尾、つがいの形成、雛の共同哺育などがある<ref>{{cite book |last=Bagemihl |first=Bruce |title=Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity |year=1999 |publisher=St. Martin's |location=New York |page=479-655}} 100種を詳細に記載。</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 縄張り、営巣と抱卵 ===
| |
| − | {{See also|{{仮リンク|鳥類の巣|en|Bird nest}}}}
| |
| − | 多くの鳥類が、繁殖期になると、ほかの同種の鳥からその縄張りを活発に防御する。縄張りの維持は、雛のための食料源の保持を意味するからである。[[海鳥]]や[[アマツバメ科|アマツバメ類]]のように、採食の縄張りを守ることのできない種は、多くの場合、かわりに集団繁殖地(コロニー、[[w:Bird colony|colony]])で繁殖する。これは捕食者からの防御手段であると考えられている。集団繁殖を行う鳥は小さな営巣場所を守り、営巣場所をめぐってほかの同種ないし異種との競争が激しくなることがある<ref>{{cite journal | last1 = Kokko | first1 = H | last2 = Harris | first2 = M | last3 = Wanless | first3 = S | year = 2004 | title = Competition for breeding sites and site-dependent population regulation in a highly colonial seabird, the common guillemot ''Uria aalge''" | url = | journal = Journal of Animal Ecology | volume = 73 | issue = 2| pages = 367–76 | doi = 10.1111/j.0021-8790.2004.00813.x }}</ref>。
| |
| − | | |
| − | [[ファイル:Male Turdus merula feeding chicks.ogv|thumb|[[クロウタドリ]]の雄が、雛に給餌している。]]
| |
| − | すべての鳥類は、体外卵として、主に[[炭酸カルシウム]]で形成された硬い卵殻を持つ[[有羊膜類|有羊膜卵]]を産む<ref name=Gill_416-423>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、416-423頁</ref>。穴や巣穴に営巣する種は、白色ないし淡色の卵を産む傾向があり、一方、開放型の巣を作るものは、[[迷彩|迷彩色]]の卵を産む。ただし、この傾向には多くの例外が存在する。地上に営巣する[[ヨタカ科|ヨタカ類]]は淡色の卵を産み、[[カモフラージュ]]は、かわりにかれらの羽衣により行われる。[[托卵]]の仮親にされる種は、托卵された卵を見つけだす可能性を向上させるために、さまざまな色の卵を産む。それによって托卵する側の雌は、その卵を仮親の卵に合わせることになる<ref>{{cite journal | last1 = Booker | first1 = L | last2 = Booker | first2 = M | year = 1991 | title = Why Are Cuckoos Host Specific? | journal = [[w:Oikos (journal)|Oikos]] | volume = 57 | issue = 3| pages = 301–09 | doi = 10.2307/3565958 | jstor=3565958}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | [[ファイル:Golden-backed Weaver.jpg|thumb|left|alt= 黒い頭をした黄色のハタオリドリが、草の葉を編んで作った巣に逆さまにぶら下がっている。|{{仮リンク|キゴロモハタオリ|en|Golden-backed Weaver}}の雄が、草を編んで精巧な吊り巣を作っている。]]
| |
| − | 鳥類は通常、{{仮リンク|鳥類の巣|en|Bird nest|label=巣}}のなかで産卵する。ほとんどの種は、椀形、ドーム形、皿形、窪み、塚(マウンド)、あるいは穴といったような<ref>{{Cite book|和書 |author=小海途銀治郎 |coauthors=和田岳 |year=2011 |title=日本 鳥の巣図鑑 - 小海途銀次郎コレクション |publisher=東海大学出版会 |series=大阪市立自然史博物館叢書 5 |isbn=978-4-486-01911-4 |pages=331-332}}</ref>、ある程度精巧な巣を作る<ref name="Hansell">Hansell M (2000). ''Bird Nests and Construction Behaviour''. University of Cambridge Press ISBN 0-521-46038-7</ref>。しかしながら、なかにはきわめて原始的なものもある。たとえば[[アホウドリ科|アホウドリ類]]の巣は、地面のかき跡以上のものではない。ほとんどの鳥は、捕食されることを避けるため、その巣を覆いのある、隠れた場所に作る。しかし、大型鳥類やコロニーを形成する鳥など、より防御力の高い鳥類は、さらに開放的な巣を作ることがある。営巣においてある種の鳥は、雛の生存を高めるために、寄生虫を減らす毒素を持つ植物による植物性素材を探し<ref>{{cite journal | last1=Lafuma | first1=L |last2=Lambrechts |first2=M |last3=Raymond |first3=M |year=2001 |title=Aromatic plants in bird nests as a protection against [[吸血動物|blood-sucking]] flying insects? |url= |journal=Behavioural Processes |volume=56 |issue=2 |pages=113–20 |doi=10.1016/S0376-6357(01)00191-7}}</ref>、また、羽毛は巣の断熱材としてよく用いられる<ref name = "Hansell"/>。鳥類のなかには巣を持たない種もあり、崖に営巣する[[ウミガラス]]は、その卵をむきだしの岩の上に生む。また、[[コウテイペンギン]]の雄は、卵をその足と体の間に保持する。巣の欠如は、地上に営巣する種で、孵化する雛が早成性 ([[w:Precocial|Precocial]]) である場合において、特に多く見られる。
| |
| − | | |
| − | [[ファイル:Eastern Phoebe-nest-Brown-headed-Cowbird-egg.jpg|thumb|alt= 藁で作られた巣に5つの白い卵と、斑点のある灰色の卵がひとつ入っている。|[[コウウチョウ]]に托卵された{{仮リンク|ツキヒメハエトリ|en|Eastern Phoebe}}の巣。]]
| |
| − | 抱卵は、雛の孵化のために温度を最適化するものであり、通常は最後の卵が産み落とされたあとに始まる<ref name=Gill_443・448>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、443頁、448頁</ref>。一夫一婦の種における抱卵の務めは、雌雄で共有されることが多いのに対し、一夫多妻の種では、片方の親(雌)が抱卵の全責務を負う。親鳥の体熱は、卵を抱いている鳥の腹ないし胸の皮膚が露出した部分である{{仮リンク|抱卵斑|en|Brood patch}}を通して卵に伝わる。抱卵はエネルギー的要求の高い行為であり、たとえば成鳥のアホウドリは、抱卵に1日あたり体重の約{{convert|83|g}}を失っていく<ref>{{cite book |last=Warham |first=John |title=The Petrels: Their Ecology and Breeding Systems |year=1990 |publisher=[[w:Academic Press|Academic Press]] |location=London |isbn=0-12-735420-4}}</ref>。[[ツカツクリ科|ツカツクリ類]]の卵を孵すための熱は、太陽、植物の腐食もしくは火山性の熱源による<ref>{{cite book | last1=Jones |first1=Darryl N. |last2=Dekker |first2=René W.R.J. |last3=Roselaar |first3=Cees S. |title=The Megapodes |series=Bird Families of the World 3 |year=1995 |publisher=[[オックスフォード大学出版局|Oxford University Press]] |location=Oxford |isbn=0-19-854651-3}}</ref>。抱卵期間は、[[キツツキ科|キツツキ類]]、[[カッコウ科|カッコウ類]]、[[スズメ目]]の鳥のおよそ10日から、アホウドリ類や[[キーウィ (鳥)|キーウィ類]]の80-90日におよぶ<ref name=Gill_448>[[#ギル3|ギル 『鳥類学』 (2009)]]、448頁</ref>。
| |
| − | | |
| − | ==== 親鳥の世話と巣立ち ====
| |
| − | 孵化の時点で雛の成長の度合いは、その種によって、晩成から早成までの範囲がある。晩成性 ([[w:Altricial|Altricial]]) の雛はいわゆる「留巣性」であり、小さく生まれてくる傾向があり、目が開いておらず、動くことができず、羽毛を持たない。孵化した時点で動くことができ、羽毛が生えそろっている早成性の雛を「離巣性」と呼ぶ。晩成性の雛は、[[体温#体温調節|体温調節]]のための助けが必要であり、早成性の雛よりも長い期間にわたって、親鳥からの給餌を受けなくてはならない。この両極のいずれでもないような雛を、半早成性 (Semi-precocial) もしくは半晩成性 (Semi-altricial) と呼ぶ。
| |
| − | [[ファイル:Calliope-nest edit.jpg|thumb|alt= ハチドリが小さな巣の縁に止まって、餌を2羽の雛のうちの1羽の口に入れている。|left|[[ヒメハチドリ]]の雌が、十分成長した雛に餌を与えている。]]
| |
| − | | |
| − | 親鳥による雛の世話の期間と性質は、その分類目や種の間で大きく異なる。ある極端な例として、[[ツカツクリ科|ツカツクリ類]]の親鳥の世話は、孵化の時点で終了する。孵化したばかりの雛は、親鳥の助けなしに巣である塚(マウンド)のなかから自身を掘り起し、また直ちに自活することができる<Ref>Elliot A. "Family Megapodiidae (Megapodes)". {{cite book |editor=del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J |title=[[w:Handbook of the Birds of the World|Handbook of the Birds of the World]] Volume 2: New World Vultures to Guineafowl |year=1994 |publisher=Lynx Edicions |location=Barcelona |isbn=84-87334-15-6}}</ref>。それとは反対に、多くの海鳥は、親鳥の世話する期間が長期にわたり、最も長いものは[[オオグンカンドリ]]で、その雛は巣立つまでに6か月かかり、さらに14か月にわたって親鳥から給餌を受ける<ref>Metz VG, Schreiber EA (2002). "Great Frigatebird (''Fregata minor'')" In ''The Birds of North America, No 681'', (Poole, A. and Gill, F., eds) The Birds of North America Inc: Philadelphia</ref>
| |
| − | | |
| − | ある種においては、両方の親鳥が雛の世話と巣立ちに関わるが、そのほか、一方の親鳥だけがその世話を務めるものもある。また種によっては、雛の養育を、同種のほかの仲間(ヘルパー、[[w:Helpers at the nest|helper]]、通常は、前回の繁殖のときの子といった繁殖つがいの近親)が手助けする場合もある<ref>{{cite journal | last1 = Ekman | first1 = J | year = 2006 | title = Family living amongst birds | url = | journal = [[w:Journal of Avian Biology]] | volume = 37 | issue = 4| pages = 289–98 | doi = 10.1111/j.2006.0908-8857.03666.x }}</ref>。このような代理育雛は、とりわけ[[カラス科|カラス類]]や[[カササギフエガラス]]、[[オーストラリアムシクイ科|オーストラリアムシクイ類]]などの[[カラス小目]]の種で一般的であるが<ref>{{Cite book|author=Cockburn A|editor=Floyd R, Sheppard A, de Barro P|title=Frontiers in Population Ecology|year=1996|publisher=CSIRO|location=Melbourne|isbn= |pages=21–42|chapter=Why do so many Australian birds cooperate? Social evolution in the Corvida}}</ref>、[[ミドリイワサザイ]]や[[アカトビ]]のように、異なる種の鳥においても観察されている。ほとんどの動物群において、雄が子の世話をすることは稀である。しかしながら、鳥類においてはきわめて一般的であり、ほかの脊椎動物群に比べて非常に多い<ref name = "Gill"/>。縄張りや営巣地の防御、抱卵、雛への給餌などは、多くの場合分担して行われるが、ときに一方が、特定の責務すべてないしそのほとんどを受け持つような[[分業]]が生ずることもある<ref>{{Cite journal |last=Cockburn|first=Andrew|year=2006|title=Prevalence of different modes of parental care in birds |doi=10.1098/rspb.2005.3458|journal=Proceedings: Biological Sciences|volume=273|issue=1592|pages=1375–83|pmid=16777726|month= June|issn=0962-8452|url=http://rspb.royalsocietypublishing.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16777726|format=Free full text|pmc=1560291|accessdate=2014-07-13}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 雛が巣立つタイミングは、実にさまざまである。[[ウミスズメ]]のような{{仮リンク|ウミスズメ属|en|Synthliboramphus}}の雛は、陸性の捕食者から逃れるために、孵化したその夜にも(孵化後1-3日)巣を離れ、親鳥について海に出る<ref>{{Cite journal |last=Gaston |first=Anthony J. |year=1994 |title=Ancient Murrelet (''Synthliboramphus antiquus'') |journal=[https://www.pwrc.usgs.gov/library/bna/default.htm The Birds of North America] |number=132 |editor=A. Poole and F. Gill |url=http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/132/articles/introduction}}</ref>。ほかにも、カモ類のように早いうちにその雛を巣から遠くに移動させる種がある。ほとんどの種において、雛は飛ぶことができる直前、あるいはその直後に巣を離れる。巣立ったあとの親鳥による世話の度合はさまざまである。アホウドリ類の雛は自分で巣を離れ、それ以上の助けは受けないが<ref>{{cite journal | last1 = Schaefer | first1 = HC | last2 = Eshiamwata | first2 = GW | last3 = Munyekenye | first3 = FB | last4 = Bohning-Gaese | first4 = K | year = 2004 | title = Life-history of two African ''Sylvia'' warblers: low annual fecundity and long post-fledging care | url = | journal = [[w:Ibis (journal)|Ibis]] | volume = 146 | issue = 3| pages = 427–37 | doi = 10.1111/j.1474-919X.2004.00276.x }}</ref>、一方、ほかの種においては巣立ち後も、ある程度補助的な給餌を続ける。雛はまた、最初の[[渡り鳥|渡り]]の際にその親鳥についていくこともある<ref>{{cite journal | last1 = Alonso | first1 = JC | last2 = Bautista | first2 = LM | last3 = Alonso | first3 = JA | year = 2004 | title = Family-based territoriality vs flocking in wintering common cranes ''Grus grus''" | url = | journal = [[w:Journal of Avian Biology]] | volume = 35 | issue = 5| pages = 434–44 | doi = 10.1111/j.0908-8857.2004.03290.x }}</ref>。
| |
| − | | |
| − | ==== 托卵 ====
| |
| − | {{Main|托卵}}
| |
| − | [[ファイル:Reed warbler cuckoo.jpg|thumb|upright|right|alt= 小さな褐色の鳥が、巣のなかのはるかに大きな灰色の鳥のくちばしに虫を運んでいる。|[[オオヨシキリ]]が、[[托卵]]された[[カッコウ]]の雛を育てている。]]
| |
| − | [[托卵]]とは、卵を産むものが、その卵の世話を別の個体の抱卵に託すことをいい、ほかのどの種類の生物よりも、鳥類の間でより一般的である<ref name="brood">{{cite book |last=Davies |first=N. B. |title=Cuckoos, Cowbirds and other Cheats |year=2000 |publisher=[[w:T. & A. D. Poyser|T. & A. D. Poyser]] |location=London |isbn=0-85661-135-2}}</ref>。托卵する鳥がその卵をほかの鳥類の巣に産んだあと、多くの場合、卵は仮親(卵を託された親)に受け入れられ、仮親の雛を犠牲にして育てられる。托卵には、自分の子を育てることができないことから、その卵を必ず異種の鳥の巣に産まなければならない真性托卵(種間托卵)と、自分で子を育てることができるにもかかわらず繁殖の結果を向上させるため、ときに同種の巣にその卵を産むことのある条件的托卵(種内托卵)がある<ref>{{cite journal |doi=10.1093/beheco/8.2.153 |last1=Sorenson |first1= Michael D. |year=1997 |title=Effects of intra- and interspecific brood parasitism on a precocial host, the canvasback, ''Aythya valisineria'' |url=http://beheco.oxfordjournals.org/cgi/reprint/8/2/153.pdf |format=PDF |journal=Behavioral Ecology |volume=8 |issue=2 |pages=153–161 |accessdate=2014-07-20}}</ref>。[[ミツオシエ科|ミツオシエ類]]、[[ムクドリモドキ科|ムクドリモドキ類]]、[[テンニンチョウ属|テンニンチョウ類]]、カモ類([[ズグロガモ]])など、約100種の鳥が真性托卵を行うが、そのなかで最も有名なのが[[カッコウ科|カッコウ類]]である。托卵する種のなかには、その仮親の雛より前に孵化するよう適応したものがあり<ref name="brood"/>、これによって仮親の卵を巣の外に押し出して壊すことや、仮親の雛を殺すことが可能になる。このことは、巣に運ばれる食料すべてが托卵の雛に与えられることを確実にする<ref>{{cite journal |last1=Spottiswoode |first1=C. N. |last2=Colebrook-Robjent |first2=J. F.R. |title=Egg puncturing by the brood parasitic Greater Honeyguide and potential host counteradaptations |journal=Behavioral Ecology |volume=18 |pages=792-799 |year=2007 |doi=10.1093/beheco/arm025 | issue=4}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | == 生態系 ==
| |
| − | 鳥類は、広範囲にわたる生態的地位を占めている<ref name="flycatcher"/>。ある種の鳥類は広食性(多食性)であるが、他方、その生息地ないし食餌の要件において高度に特化した鳥類もある。たとえば森林のような単一の生息環境においても、それぞれ異なる鳥類によって占められる生態的ニッチはさまざまであり、ある種は[[林冠]]で採餌し、別のものは樹冠の下で、またそのほかに林床で採餌する種もある。森林の鳥は、{{仮リンク|食虫動物|en|Insectivore|label=食虫性}}であったり、{{仮リンク|果食動物|en|Frugivore|label=果食性}}、[[蜜食動物|蜜食性]]であったりする。水鳥は、一般に魚を採食したり、植物を食べたり、あるいはほかの鳥から奪い取る海賊行動(盗賊的寄生)すなわち[[盗み寄生]]により採餌する。猛禽類は、哺乳類ないしほかの鳥類の捕食に特化し、[[ハゲワシ|ハゲワシ類]]は[[腐肉食]]に特化している。[[w:Avivore|Avivore]] は、鳥類の捕食に特化した動物たちである。
| |
| − | | |
| − | ある種の蜜食性の鳥類は、重要な受粉媒介者であり、また多くの果食性の鳥類が、種子の散布において重要な役割を果たしている<ref name="Clout">{{cite journal |last1=Clout |first1=M. N. |last2=Hay |first2=J. R. |year=1989 |title=The importance of birds as browsers, pollinators and seed dispersers in New Zealand forests |url=http://nzes-nzje.grdev.co.nz/free_issues/NZJEcol12_s_27.pdf |format=PDF |journal=New Zealand Journal of Ecology |volume=12 |issue= |pages=27–33 |accessdate=2014-07-21}}</ref>。植物と受粉する鳥類は[[共進化]]していることが多く<ref>{{cite journal |last1=Gary Stiles |first1=F. |title=Geographical Aspects of Bird-Flower Coevolution, with Particular Reference to Central America |journal=Annals of the Missouri Botanical Garden |volume=68 |issue=2 |pages=323–351 |year=1981 |doi=10.2307/2398801 |jstor=2398801}}</ref>、なかには花の主な受粉者が、その蜜を得ることができる唯一の種である場合もある<ref>{{cite journal |last1=Temeles |first1=Ethan J. |last2=Linhart |first2=Yan B. |last3=Masonjones | first3=Michael |last4=Masonjones |first4=Heather D. |year=2002 |title=The Role of Flower Width in Hummingbird Bill Length–Flower Length Relationships |url=http://www.amherst.edu/~ejtemeles/Temeles%20et%20al%202002%20biotropica.pdf |format=PDF |journal=Biotropica |volume=34 |issue=1 |pages=68–80 |accessdate=2014-07-21}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類は、島嶼の生態系に対して重要な役割を演ずることが多い。鳥類はよく、哺乳類がいない諸島におよぶ。これらの島々では、一般に大型動物によって演じられる生態的役割を、鳥類が果たすこともある。たとえばニュージーランドでは、[[ニュージーランドバト]]({{lang-mi|kererū}})や[[ハシブトホオダレムクドリ]]({{lang-mi|Kōkako}})が今日そうであるように、[[モア|モア類]]が主要な草食者であった<ref name="Clout"/>。今日、ニュージーランドの植物は、絶滅したモアから自身を守るために進化した防御的な適応を保持している<ref>{{cite journal |last1=Bond |first1=William J. |last2=Lee |first2=William G. |last3=Craine |first3=Joseph M. |title=Plant structural defences against browsing birds: a legacy of New Zealand's extinct moas |journal=Oikos |volume=104 | pages=500–08 |year=2004 |doi=10.1111/j.0030-1299.2004.12720.x |issue=3}}</ref>。[[海鳥]]の営巣もまた、島嶼やその周囲の海域の生態系に影響を与えることがある。これは主に大量の[[グアノ]](鳥糞石)の集積により、その地域の土壌<ref>{{cite journal |last1=Wainright |first1=S. C. |last2=Haney |first2=J. C. |last3=Kerr |first3=C. |last4=Golovkin |first4=A. N. |last5=Flint |first5=M. V. |year=1998 |title=Utilization of nitrogen derived from seabird guano by terrestrial and marine plants at St. Paul, Pribilof Islands, Bering Sea, Alaska |url= http://www.springerlink.com/index/DN8D70RYM7TUF42P.pdf |journal=Marine Ecology |volume=131 |issue=1 |pages=63–71}}</ref>、および周辺海域が豊かになることによる<ref>{{cite journal |doi=10.3354/meps032247 |last1=Bosman |first1=A. L. |last2=Hockey |first2=P. A. R. |year=1986 |title=Seabird guano as a determinant of rocky intertidal community structure |url=http://www.int-res.com/articles/meps/32/m032p247.pdf |format=PDF |journal=Marine Ecology Progress Series |volume=32 |issue= |pages=247–257 |accessdate=2014-07-21 }}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類生態野外調査 ([[w:Avian ecology field methods|Avian ecology field methods]]) の手段として、個体数の集計(カウント)、巣の監視活動(モニタリング)、捕獲と[[鳥類標識調査|標識調査]](マーキング)など、さまざまな方法が用いられている。
| |
| − | | |
| − | == 人間との関係 ==
| |
| − | [[ファイル:Industrial-Chicken-Coop.JPG|thumb|alt= たくさんの白いニワトリがそれぞれのケージに入れられて、暗い納屋のなかの2段に積まれている。|right|[[ニワトリ]]の[[集約農業|工業的飼育]]。]]
| |
| − | | |
| − | 鳥類は非常によく見られ、一般的な動物群であることから、人類はヒトの黎明期から鳥類との関係を持ってきた<ref>{{Cite book |last=Bonney |first=Rick |last2=Rohrbaugh, Jr. |first2=Ronald |title=Handbook of Bird Biology |place=Princeton, NJ |publisher=Princeton University Press |year=2004 |edition= Second |isbn=0-938027-62-X}}</ref>。ときにこうした関係は、ボラナ族 ([[w:Borana Oromo people|Borana]]) のようなアフリカの民族と[[ミツオシエ科|ミツオシエ類]]の間における協同のハチミツ採集のように、[[相利共生]]のものもある<ref>{{cite journal |last1=Dean |first1=W. R. J. |last2=Siegfried |first2=W. Roy |last3=MacDonald |first3=I. A. W. |year=1990 |title=The Fallacy, Fact, and Fate of Guiding Behavior in the Greater Honeyguide |url=http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1523-1739.1990.tb00272.x Blackwell-PDF |journal=Conservation Biology |volume=4 |number=1 |pages=99-101}}</ref>。他方、[[イエスズメ]]のような種が人間の活動から恩恵を得ているように、[[片利共生]]のこともある<ref>{{cite journal | last1= Singer | first1= R. | last2= Yom-Tov | first2= Y. | title= The Breeding Biology of the House Sparrow Passer domesticus in Israel | journal= Ornis Scandinavica | volume= 19 | issue= 2 | pages= 139–44 | year= 1988 |doi= 10.2307/3676463 | jstor=3676463}}</ref>。何種もの鳥類が、商業的に深刻な[[害鳥#農林水産業に対する害|農業害鳥]]とされており<ref>{{Cite journal |doi = 10.1111/j.1474-919X.1990.tb01048.x |last=Dolbeer |first=R. A. |year=1990 | title=Ornithology and integrated pest management: Red-winged blackbirds ''Agleaius phoeniceus'' and corn |url = |journal=[[w:Ibis (journal)|Ibis]] |volume=132 |issue=2 |pages=309–322}}</ref>、また[[バードストライク|航空上の危険]]をもたらす場合もある<ref>{{Cite journal |last1=Dolbeer |first1=Richard A. |last2=Belant |first2=Jerrold L. |last3=Sillings |first3=Janet L. |year=1993 |title=Shooting Gulls Reduces Strikes with Aircraft at John F. Kennedy International Airport |url=http://www.aphis.usda.gov/wildlife_damage/nwrc/publications/93pubs/93-16.pdf |format=PDF |journal=Wildlife Society Bulletin |volume=21 |issue = |pages=442–450}}</ref>。人間の活動が鳥類にとって有害な場合もあり、たくさんの種の鳥類が絶滅の危機にさらされている([[狩猟]]、{{仮リンク|動物の鉛中毒|en|Animal lead poisoning|label=鉛中毒}}、[[農薬]]、[[轢死]]、それに家畜の[[ネコ]]や[[イヌ]]による捕食が一般的死因である)。
| |
| − | | |
| − | 鳥類は媒介者として、[[オウム病]]、[[サルモネラ症]]、[[カンピロバクター症]]、マイコバクテリア(鳥[[結核]]症)、[[トリインフルエンザ|鳥インフルエンザ]]、[[ジアルジア症]]、[[クリプトスポリジウム症]]などの疾患を、遠距離を介して広めることがある。これらのなかには、ヒトによって媒介され得る[[人獣共通感染症]]もある<ref>{{cite journal | doi = 10.3121/cmr.1.1.5 | last1 = Reed | first1 = KD | last2 = Meece | first2 = JK | last3 = Henkel | first3 = JS | last4 = Shukla | first4 = SK | title = Birds, migration and emerging zoonoses: west nile virus, lyme disease, influenza a and enteropathogens | journal = Clinical medicine & research | volume = 1 | issue = 1 | pages = 5–12 | year = 2003 | pmid = 15931279 | pmc = 1069015 }}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 経済的重要性 ===
| |
| − | 食肉や採卵のために飼育された鳥類は、家禽と呼ばれ、人間によって消費される動物性タンパク質の最大の供給源であり、2003年には全世界で約 {{Nowrap|7,600万トン}}の家禽と<ref>{{cite book |last1=Brown|first1=Lester|title=Outgrowing the Earth: The Food Security Challenge in an Age of Falling Water Tables and Rising Temperatures |url=http://www.earth-policy.org/datacenter/xls/book_ote_ch3_2.xls |year=2005 |publisher=earthscan |isbn=978-1-84407-185-2 |chapter=3: Moving Up the Food Chain Efficiently. |accessdate=2014-07-23}}</ref>、{{Nowrap|6,100万トン}}の卵が生産された<ref>{{cite web|url=http://www.earthpolicy.org/mobile/books/out/ote3_3?phpMyAdmin=1d6bec1fea35111307d869d19bcd2ce7 |title=Shifting protein sources: Chapter 3: Moving Up the Food Chain Efficiently. |publisher=Earth Policy Institute |accessdate=2014-07-23}}</ref>。家禽の消費においては、[[ニワトリ]]が大部分を占めるが、シチメンチョウ、ガン、カモも比較的一般である。また鳥類の多くの種が、食用のために狩猟の対象となる。鳥類の狩猟(ハンティング)は、きわめて未開発の地域を除いて、主に娯楽的活動である。南・北アメリカにおける最も重要な狩猟鳥は水鳥であるが<ref>{{Cite journal |last1=Simeone |first1=Alejandro |last2=Navarro |first2=Ximena |year=2002 |title=Human exploitation of seabirds in coastal southern Chile during the mid-Holocene |url=http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-078X2002000200012&lng=es&nrm=iso&tlng=en |journal=Rev. Chil. Hist. Nat |volume=75 |issue=2 | pages=423–31 |doi=10.4067/S0716-078X2002000200012 |accessdate=2014-07-26}}</ref>、これ以外にも広く[[キジ亜科 (Sibley)|キジ類]]、[[ウズラ属|ウズラ類]]、ヤマウズラ類 ([[w:Partridge|Partridge]])、[[シチメンチョウ属|シチメンチョウ類]]、[[ライチョウ亜科|ライチョウ類]]<ref name=Keane_et_al_2005>{{cite journal |last1=Keane |first1=Aidan |last2=Brooke |first2=M.de L. |last3=McGowan |first3=P.J.K. |title=Correlates of extinction risk and hunting pressure in gamebirds (Galliformes) |journal=Biological Conservation |volume=126 |issue=2 |pages=216–233 |year=2005 |doi=10.1016/j.biocon.2005.05.011}}</ref>、[[ハト科|ハト類]]、タシギ類 ([[w:Snipe|Snipe]])、ヤマシギ類 ([[w:Woodcock|Woodcock]]) などが狩猟の対象となっている。また[[オーストラリア]]や[[ニュージーランド]]では、{{仮リンク|マトンバード猟|en|Muttonbirding}}(海鳥であるミズナギドリ類の雛〈マトンバード、Mutton Bird〉を、季節的に食用のため捕獲すること)も一般的である<ref>{{cite journal |last=Hamilton |first=Sheryl |year=2000 |title=How precise and accurate are data obtained using an infra-red scope on burrow-nesting sooty shearwaters ''Puffinus griseus''? | url = http://www.marineornithology.org/PDF/28_1/28_1_1.pdf |format=PDF |journal=Marine Ornithology |volume=28 |number= 1 |pages=1–6 |accessdate=2014-07-26}}</ref>。マトンバード猟のような狩猟は維持され得るが、狩猟は数多くの種を絶滅あるいは絶滅の危険にさらすことに繋がる<ref name=Keane_et_al_2005 />。
| |
| − | | |
| − | [[ファイル:FishingCormorants.jpg|thumb|upright|alt= 筏にたくさんの黒い鳥を乗せて、筏を操る竿を手にした漁師の絵|アジアの漁師による鵜を使った漁([[鵜飼い]])は、急激に数を減らしているが、一部の地域では観光の呼び物として存続している。]]
| |
| − | ほかに鳥類から得られる商業的に価値のある製品としては、衣類や寝具の断熱材として用いられる羽毛(特にガン・カモ類の{{仮リンク|綿羽|en|Down feather}})や、[[リン]]、[[窒素]]の貴重な供給源となる海鳥の糞([[グアノ]]、鳥糞石)などがある。[[太平洋戦争_(1879年-1884年)|太平洋戦争]](1879年-1884年)は、ときに硝石戦争(グアノ戦争)とも呼ばれ、一部では鳥糞石の鉱床の権益をめぐって戦いが行われた<ref>{{cite web |url=http://www.zum.de/whkmla/military/19cen/guanowar.html |title=The Guano War of 1865–1866 |publisher=World History at KMLA |accessdate=2014-07-26}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類は、人間によってペットとして、また実用的な目的のために飼われている。[[オウム目|オウム類]]や[[ムクドリ科|ムクドリ類]]のような色彩豊かな鳥類は、飼育下で繁殖させたりペットとして飼われたりするが、こういった行為が、一部の[[絶滅危惧種]]の違法な取引に結びついている<ref>{{cite journal |last1=Cooney |first1=Rosie |last2=Jepson |first2=Paul |year=2006 |title=The international wild bird trade: what's wrong with blanket bans? |url=http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext?fulltextid=409231 |doi=10.1017/S0030605306000056 |journal=Oryx |volume=40 |issue=1 |pages=18–23 }}</ref>。[[ハヤブサ属|ハヤブサ類]]および[[ウ科|ウ類]]は、長きにわたってそれぞれ[[狩猟]]や[[漁業]]に使われてきた。[[伝書鳩]]は、少なくとも西暦1年から使われており、その重要性は[[第二次世界大戦]]まで続いた。今日ではそのような活動は、趣味、娯楽、観光<ref>{{Cite journal |doi=10.2307/4140937 |last1=Manzi |first1=Maya |last2=Coomes |first2=Oliver T. |year=2002 |title=Cormorant fishing in Southwestern China: a Traditional Fishery under Siege. (Geographical Field Note) |url=http://findarticles.com/p/articles/mi_go1895/is_200210/ai_n8674873 |journal=Geographic Review |volume=92 |number=4 |pages=597–603 |jstor=4140937 |archiveurl=http://archive.is/ceAU |archivedate=2012-05-29}}</ref>、あるいは{{仮リンク|鳩レース|en|Pigeon racing}}といったスポーツがより一般的である。
| |
| − | | |
| − | アマチュアの鳥愛好家(バーダー、より一般には[[野鳥観察|バードウォッチャー]]と呼ばれる)は何百万人にものぼる<ref>{{cite journal |last=Pullis La Rouche |first=Genevieve |title=[http://jncc.defra.gov.uk/PDF/pub07_waterbirds_part6.2.5.pdf Birding in the United States: a demographic and economic analysis] |year=2006 |publisher=[[w:The Stationery Office|Stationery Office]] |location=Edinburgh, UK |journal=Waterbirds around the world (JNCC.gov.uk) |format=PDF |editor=G.C. Boere, C.A. Galbraith and D.A. Stroud |pages=841–846}}</ref>。自宅所有者のなかには、住居近くに鳥の餌台(バードフィーダー)を設置して、さまざまな種の鳥を引き寄せようとする者が多くいる。鳥類への給餌 ([[w:Bird feeding|Bird feeding]]) は数百万ドル産業にまで成長しており、たとえばイギリスの家庭のおよそ75%が、冬季中に鳥類のために何らかの餌を与えるとされる<ref>{{cite journal |last1=Chamberlain |first1=Dan E. |last2=Vickery |first2=Juliet A. |last3=Glue |first3=David E. |last4=Robinson |first4=Robert A. |last5=Conway |first5=Greg J. |last6=Woodburn |first6=Richard J. W. |last7=Cannon |first7=Andrew R. |year=2005 |title=Annual and seasonal trends in the use of garden feeders by birds in winter |url=http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1474-919x.2005.00430.x |doi=10.1111/j.1474-919x.2005.00430.x |journal=[[w:Ibis (journal)|Ibis]] |volume=147 |issue=3 | pages=563–575}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 宗教、伝承と文化 ===
| |
| − | [[ファイル:Vogel Drei (Meister der Spielkarten).jpg|thumb|upright|left|alt= 3羽の長い足と長い頸を持った鳥の木版画|[[w:Master of the Playing Cards|Master of the Playing Cards]] による「3羽の鳥」 ("The 3 of Birds")、15世紀、ドイツ。]]
| |
| − | | |
| − | 鳥類は、[[伝承]]、[[宗教]]、そして[[大衆文化]]において突出した、多様な役割を演じている<ref>{{Cite journal |和書 |author=山田仁史 |year=2013 |date=2013-11-26 |title=媒介者としての鳥 - その神話とシンボリズム |journal=BIOSTORY (ビオストーリー) |issue=20 |publisher=[[誠文堂新光社]] |isbn=978-4-416-11314-1}} {{要ページ番号|date=2016-05-06}}</ref>。[[宗教]]において、鳥類は[[神性|神]]の[[使者]]あるいは[[司祭]]や指導者としての役割を果たすこともある。たとえば[[マケマケ]]信仰では、[[イースター島]]の[[鳥人]](タンガタ・マヌ)が首長としての役目を果たし<ref>{{Cite journal |last1=Routledge |first1=Scoresby |last2=Routledge |first2=Katherine |year=1917 |title=The Bird Cult of Easter Island |url= |journal=Folklore |volume=28 |issue=4|pages=337–355}}</ref>、また2羽の[[ワタリガラス]]である[[フギンとムニン]]の場合には、かれらは北欧の神[[オーディン]]の耳に情報をささやく<ref>{{cite journal |last=Chapell |first=Jackie |title=Living with the Trickster: Crows, Ravens, and Human Culture |url=http://www.plosbiology.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.0040014&representation=PDF |format=PDF |journal=PLoS Biology |volume=4 |issue=1 | pages=16–17 |year=2006 |doi=10.1371/journal.pbio.0040014 |accessdate=2014-07-27}}</ref>。[[イタリアの歴史|古代イタリア]]のいくつかの文明、特に[[エトルリア]]や[[古代ローマ|ローマ]]の宗教において、司祭は占い(鳥卜、augury)に従事し、あるいは「吉兆」"auspicious" という単語の由来となった「鳥を観察する人、予言者」 "auspex" ([[アウグル]]、augur、鳥卜官)が、事象を予言するために鳥の活動を観察しながら、鳥たちの言葉を[[通訳]]した<ref>{{cite book |last=Ingersoll |first=Ernest |year=1923 |title=[https://archive.org/details/birdsinlegendfab00inge Birds in legend, fable and folklore] |publisher=Longmans, Green and co |page=214}}</ref>。鳥類はまた、[[ヨナ]]({{lang-he|'''יוֹנָה'''}}、[[鳩]]〈はと〉)が、伝統的に[[ハト科|ハト類]]を連想させる恐怖、服従、哀悼、そして美を形象化するように、{{仮リンク|宗教的象徴|en|Religious symbolism}}としての役割を果たすこともある<ref>{{cite journal |last=Hauser |first=Alan Jon |title=Jonah: In Pursuit of the Dove |journal=Journal of Biblical Literature |volume= 104 |number=1 |pages=21–37 |year=1985 |publisher=[[w:Society of Biblical Literature|The Society of Biblical Literature]] |doi=10.2307/3260591 |jstor=3260591}}</ref>。鳥類は、インドの[[ドラヴィダ人]]によって[[地母神|母なる大地]]のように考えられている[[インドクジャク]]の場合のように、かれら自身が神格化されることもある<ref>{{cite journal |last=Thankappan Nair |first=P. |title=The Peacock Cult in Asia |journal=Asian Folklore Studies |volume=33 |number=2 | pages=93–170 | year=1974 |doi=10.2307/1177550 | jstor=1177550}}</ref>。一部にはまた、伝説の鳥 [[ロック鳥|ロック]]や、[[マオリ]]の伝説的な鳥ポウアカイ (''[[w:Poukai|Pouākai]]'') など、人をさらうことができるほど巨大な鳥として、怪物と考えられてきた鳥もある<ref>{{Cite book |和書 |last1=Tennyson |first1=Alan |year=2006 |title=Extinct Birds of New Zealand |publisher=Te Papa Press |location=Wellington |isbn=978-0-909010-21-8}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | [[ファイル:17.6-24-1974-Cuerda-seca-flisepanel.jpg|thumb|鳥類が描かれた色鮮やかな[[タイル]]([[ガージャール朝]])。]]
| |
| − | 鳥類は、先史時代より文化や芸術の主題に取り上げられており、それらは早期の[[洞窟壁画]]にも描かれている<ref>{{cite journal |last=Meighan |first=Clement W. |title=Prehistoric Rock Paintings in Baja California |journal=American Antiquity |volume=31 |number=3 |pages=372–392 |year=1966 |doi=10.2307/2694739 | jstor=2694739}}</ref>。のちに鳥類は、[[ムガル帝国]]や[[イランの歴史|ペルシア]]の皇帝の壮麗な[[孔雀の玉座]]に見られるように、宗教あるいは[[象徴]]的芸術やデザインのなかで使われるようになった<ref>{{cite journal |last=Clarke |first=Caspar Purdon |year= 1908 |title=A Pedestal of the Platform of the Peacock Throne |journal=The Metropolitan Museum of Art Bulletin |volume=3 |number=10 |pages=182–183 |doi=10.2307/3252550 |jstor=3252550}}</ref>。鳥類に対する科学的関心の到来によって、たくさんの鳥類の絵画が書籍のために委託された。これらの鳥類画家のなかで最も有名なのが[[ジョン・ジェームズ・オーデュボン]]であった。北アメリカの鳥類を描いた『[[アメリカの鳥類]]』 ''The Birds of America'' (1827–1839) はヨーロッパで商業的大成功を収め、のちに彼の名は、全米オーデュボン協会 ([[w:National Audubon Society|National Audubon Society]]) に引継がれている<ref>{{cite journal |和書 |author=柴崎文一 |title=オーデュボンのアメリカ自然誌 |url=https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/3962/1/ShibasakiAudubon.pdf |format=PDF |date=2009-04-6 |journal=明治大学人文科学研究所紀要 ([https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/明治大学学術成果[[リポジトリ]]])|accessdate=2014-07-27}}</ref><ref>{{cite journal |last=Boime |first=Albert |title=John James Audubon: a birdwatcher's fanciful flights |journal=Art History |volume=22 |issue=5 |pages=728–755 |year=1999 |doi=10.1111/1467-8365.00184}}</ref>。鳥類はまた、詩文においても重要な象徴である。たとえば[[ホメーロス]]はその作品『[[オデュッセイア]]』に[[サヨナキドリ]](ナイチンゲール)を取り入れており、[[ガイウス・ウァレリウス・カトゥルス|カトゥルス]]は作品『[[w:Catullus 2|Catullus 2]]』のなかで、[[スズメ]]をエロティックな象徴として扱っている<ref>{{Cite journal |last=Chandler |first=Albert R. |year=1934 |title=The Nightingale in Greek and Latin Poetry |journal=The Classical Journal |volume=30 |number=2| pages=78–84}}</ref>。[[サミュエル・テイラー・コールリッジ]]の『老水夫行』 ''[[w:The Rime of the Ancient Mariner|The Rime of the Ancient Mariner]]'' では、アホウドリと水夫との関係が中心的テーマであり、ここからアホウドリが「重荷」を意味する[[メタファー|隠喩]]表現 '[[w:Albatross (metaphor)|Albatross]]' へと繋がった<ref>{{cite journal |last=Lasky |first=Edward D. |title=A Modern Day Albatross: The Valdez and Some of Life's Other Spills |journal=The English Journal |volume= 81 |number=3 |pages=44–46 |year=1992 |doi=10.2307/820195 |jstor=820195}}</ref>。そのほか鳥類に由来する[[英語]]の隠喩には、たとえば[[ハゲタカファンド]] ([[w:Vulture fund|vulture fund]]) やハゲタカ投資家 (vulture investor) などがあり、ハゲワシ類の屍肉食から来た表現である<ref>{{Cite journal |last=Carson |first=A. Scott |year=1998 |title=Vulture Investors, Predators of the 90s: An Ethical Examination |url=http://www.springerlink.com/index/W676R8803NL06L38.pdf |journal=Journal of Business Ethics |volume=17 |issue=5 |pages=543–555}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | さまざまな種の鳥類に対する認識は、文化によってしばしば異なる。[[フクロウ目|フクロウ類]]は、アフリカの一部では[[運|不運]]、[[ウイッチクラフト]]([[魔女]]術)、そして[[死]]と結びつけられているが<ref>{{Cite journal |last1=Enriquez |first1=Paula L. |last2=Mikkola |first2=Heimo |year=1997 |title=Comparative study of general public owl knowledge in Costa Rica, Central America and Malawi, Africa |url= http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nc190/gtr_nc190_160.pdf |format=PDF |journal= [http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nc190/gtr_nc190.pdf Biology and conservation of owls of the Northern Hemisphere. General Technical Report NC-190. 2nd Owl Symposium] |publisher=[[w:United States Forest Service|USDA Forest Service]] |location=St. Paul, Minnesota |accessdate=2014-07-27}} </ref>、ヨーロッパでは広く賢者とも見なされている<ref>{{Cite web |last=Lewis |first=Deane |year=2005 |title=Owls in Mythology & Culture |url= http://www.owlpages.com/articles.php?section=Owl+Mythology&title=Myth+and+Culture |work=The Owl Pages |publisher=Owlpages.com |accessdate=2014-07-27}}</ref>。[[ヤツガシラ]]は、[[古代エジプト]]では神聖視されており、[[ペルシア]]では[[美徳]]の[[象徴]]とされたが、一方ヨーロッパでは広く[[泥棒]]であるとされ、[[スカンディナヴィア]]では[[戦争]]の先駆けと考えられた<ref>{{Cite journal |last=Dupree |first=Hatch |year=1974 |title=An Interpretation of the Role of the Hoopoe in Afghan Folklore and Magic |url= |journal=Folklore |volume=85 |issue=3|pages=173–193 }}</ref>。
| |
| − | | |
| − | === 保全 ===
| |
| − | [[ファイル:California-Condor3-Szmurlo edit.jpg|thumb|right|alt= 羽のない頭部に鉤状のくちばしを持った大型の黒い鳥|upright|[[カリフォルニアコンドル]]は、一時わずか22羽を数えるのみとなったが、保全対策によって今日では300羽以上にまで、その数を増やした。]]
| |
| − | {{Main|w:Bird conservation}}
| |
| − | {{See also|{{仮リンク|第四紀後期の先史時代の鳥類|en|Late Quaternary prehistoric birds}}|{{仮リンク|絶滅鳥類の一覧|en|List of extinct birds}}|{{仮リンク|猛禽類の保全|en|Raptor conservation}}}}
| |
| − | 人間の活動は、[[ツバメ]]や[[ホシムクドリ]]など、ごく一部の種の拡大を許すものであったが、そのほかの多くの種においては、個体数の減少ないし[[絶滅]]を引き起こしている。1600年以来およそ130種(128種<ref name=Yamashina2006_16/>ないし131種<ref name=Gill_626/>、以前の分類では約80種<ref name=Peterson_176>[[#ピーターソン|ピーターソン『鳥類』 (1971)]]、176頁</ref><ref>{{Cite book |last=Fuller |first=Errol |year=2000 |title=Extinct Birds |edition=2nd. |publisher=[[オックスフォード大学出版局|Oxford University Press]] |location=Oxford, New York |isbn=0-19-850837-9}}</ref>)の鳥類が絶滅してしまったが、人間が引き起こした最も劇的な鳥類の絶滅は、[[メラネシア]]、[[ポリネシア]]、[[ミクロネシア]]の島嶼への人間の入植に伴って起きたもので、750から1,000種を根絶してしまったと推定されている<ref>{{Cite book |last=Steadman |first=David |year=2006 |title=Extinction & Biogeography of Tropical Pacific Birds |publisher=University of Chicago Press |isbn=978-0-226-77142-7}}</ref>。島嶼の鳥類は、外界から隔絶した環境に適応した[[固有種]](当然個体数は少ない)が多く、それらの種は人間や人間の持ち込んだ[[ネコ]]等の家畜などの外来種、およびそれらが引き起こす環境の変化に対して、非常に脆弱である。多くの鳥類が世界規模で個体数を減らしており、2009年には、[[バードライフ・インターナショナル]]と[[国際自然保護連合]] (ICUN) によって1,227種が[[w:Threatened species|絶滅危惧種]]のリストに掲げられた<ref>{{cite web |title=BirdLife International announces more Critically Endangered birds than ever before |publisher=[[バードライフ・インターナショナル|Birdlife International]] |date=14 May 2009 |url=http://www.birdlife.org/news/pr/2009/05/red_list.html |accessdate=15 May 2009}}</ref><ref>{{cite news |url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8045971.stm |first=Mark |last=Kinver |title=Birds at risk reach record high |publisher= BBC News Online |date=2009-05-13 |accessdate=2014-07-28}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 鳥類への人間による脅威として、最も一般的にあげられるのが、生息地の喪失(生息環境の破壊、[[w:Habitat destruction|Habitat destruction]])である<ref>{{Cite book |editor=Norris K, Pain D |year=2002 |title=Conserving Bird Biodiversity: General Principles and their Application |publisher=Cambridge University Press |isbn=978-0-521-78949-3}}</ref>。このほかの脅威としては、乱獲や、構造物との衝突、あるいは[[延縄]]漁業の[[混獲]]などの突発的な死亡<ref>{{Cite journal |last=Brothers |first=Nigel |year=1991 |title=Albatross mortality and associated bait loss in the Japanese longline fishery in the Southern Ocean |url= |journal=Biological Conservation |volume=55 |issue=3 |pages=255–268 |doi=10.1016/0006-3207(91)90031-4}}</ref>、[[環境汚染]]([[石油流出|原油流出]]や[[殺虫剤]]の使用など)、持ち込まれた[[外来種]]による競合や捕食<ref>{{cite journal |last1=Wurster |first1=D. H. |last2=Wurster |first2=C. F. |last3=Strickland |first3=W. N. |year=1965 |title=Bird Mortality Following DDT Spray for Dutch Elm Disease |url= |journal=Ecology |volume=46 |number=4 |pages=488–499 |doi=10.2307/1934880}}; {{cite journal |title= Bird Mortality after Spraying for Dutch Elm Disease with DDT | year=1965 |last1=Wurster |first1=C. F. |last2=Wurster |first2=D. H. |last3=Strickland |first3=W. N. |journal=Science |volume=148 |number=3666 |pages=90–91 |doi=10.1126/science.148.3666.90}}</ref>、それに気候変動などがある<ref>{{cite journal |last1=Blackburn |first1=Tim M. |last2=Cassey |first2=Phillp |last3=Duncan |first3=Richard P. |last4=Evans |first4=Karl L. |last5=Gaston |first5=Kevin J. |year=2004 |title=Avian Extinction and Mammalian Introductions on Oceanic Islands |url= |journal=Science | volume = 305 | issue = 5692| pages = 1955–58 | doi = 10.1126/science.1101617 | pmid=15448269}}</ref>。
| |
| − | | |
| − | 政府や[[保全生態学|保護活動]]団体は、鳥類を保護するために働いており、生息地の保護および[[復元生態学|回復]]({{仮リンク|生息域内保全|en|In situ conservation}})させる法律を通過させること、あるいは再移入のための飼育個体による安定個体群の確立({{仮リンク|生息域外保全|en|Ex-situ conservation}})を図るなどの活動を行っている。このようなプロジェクトのなかには、いくつか成功を収めたものもあり、ある研究では、環境保全活動によって[[カリフォルニアコンドル]]や{{仮リンク|ノーフォークインコ|en|Norfolk parakeet}}など、そのままでは1994年から2004年の間に絶滅してしまったはずの鳥類16種が救われたと推定している<ref>{{cite journal |last1=Butchart |first1=Stuart H.M. |last2=Stattersfield |first2=Alison J. |last3=Collar |first3=Nigel J. |year=2006 |title=How many bird extinctions have we prevented? |url=http://www.birdlife.org/news/news/2006/08/butchart_et_al_2006.pdf |journal=Oryx |volume=40 |issue=3 |pages=266–278 |doi= 10.1017/S0030605306000950}}</ref>。
| |
| | | | |
| | + | 約 1億5000万年ほど前の[[ジュラ紀]]後期には現れていたとみられる。生活様式は多様で,[[極地]]から[[熱帯]]まで,また地上,水中,空中など地球上のほとんどの環境に生息する。現生のものは約 1万種,40目 240科に分類されている。 |
| | + | |
| | == 脚注 == | | == 脚注 == |
| − | {{Reflist|2}} | + | {{Reflist}} |
| − | | |
| − | == 参考文献 ==
| |
| − | * {{Cite book |和書 |author=[[山岸哲]] |year=2002 |title=オシドリは浮気をしないのか - 鳥類学への招待 |publisher=[[中央公論社]] |series=[[中公新書]] |isbn=4-12-101628-9 |ref=山岸2002}}
| |
| − | * {{Cite book |和書 |author=[[樋口広芳]] |year=2016 |title=鳥ってすごい! |publisher=[[山と溪谷社]] |series=ヤマケイ新書 |isbn=978-4-635-51034-9 |ref=樋口2016}}
| |
| − | * {{Cite book |和書 |author=[[山階鳥類研究所]] |year=2004 |title=鳥の雑学辞典 |publisher=[[日本実業出版社]] |isbn=4-534-03709-0 |ref=山階2004}}
| |
| − | * {{Cite book |和書 |author=山階鳥類研究所 |year=2006 |title=われら地球家族 鳥と人間 |publisher=[[NHK出版]] |isbn=4-14-081105-6 |ref=山階2006}}
| |
| − | * {{Cite book |和書 |author=フランク・B. ギル ([[w:Frank Gill (ornithologist)|Frank B. Gill]]) |editor=山岸哲監修 |translator=山階鳥類研究所 |year=2009 |title=鳥類学 (Ornithology) |edition=(原書第3版) |publisher=新樹社 |isbn=978-4-7875-8596-7 |ref=ギル3}}
| |
| − | * {{Cite book |和書 |author=ロジャー・ピーターソン ([[w:Roger Tory Peterson|Roger Peterson]]) |editor=タイム ライフ ブックス編集部 |translator=[[山階芳麿]] |year=1971 |title=ライフ ネーチュア ライブラリー 鳥類 |edition=改訂版 |publisher=[[タイム (雑誌)|TIME]] |series=タイム ライフ ブックス |isbn= |ref=ピーターソン}}
| |
| − | * {{Cite book |和書 |editor=山岸哲・森岡弘之・樋口広芳監修 |year=2004 |title=鳥類学辞典 |publisher=[[昭和堂]] |isbn=4-8122-0413-5 |ref=鳥類学辞典}}
| |
| − | * {{Cite book |和書 |editor=[[真鍋真]]監訳 |translator=藤原慎一・松本涼子 |year=2015 |title=恐竜学入門 - かたち・生態・絶滅 |edition=(原書第2版) |publisher=東京科学同人 |isbn=978-4-8079-0856-1 |ref=恐竜学入門}}
| |
| | | | |
| | == 関連項目 == | | == 関連項目 == |
| − | {{Portal|鳥類}} | + | {{鳥類}} |
| − | {{鳥類関連リスト}}
| |
| − | * [[:Category:鳥類画像|鳥類の画像一覧]]
| |
| − | * [[:Category:化石鳥類|化石鳥類の一覧]]
| |
| | | | |
| − | == 外部リンク ==
| |
| − | {{Sister project links|wikt=鳥|b=特別:検索/鳥|q=鳥|s=特別:検索/鳥|commons=Aves|commonscat=Aves|n=特別:検索/鳥|v=特別:検索/鳥|d=Q5113|species=Aves}}
| |
| − | {{Wikibooks|en:Dichotomous Key/Aves|鳥類}}
| |
| − | *[http://www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp?lang=EN&pg=home Avibase] — 世界の鳥類のデータベース
| |
| − | *[http://www.birdlife.org/ Birdlife International] — 全世界での鳥類の保護を主な活動としており、絶滅危惧種に関するおよそ250,000件の記録についてのデータベースを持っている。
| |
| − | *[http://people.eku.edu/ritchisong/birdbiogeography1.htm Bird biogeography]
| |
| − | *[http://www.audubon.org/bird/index.html Birds and Science] [[w:National Audubon Society|全米オーデュボン協会]]が運営するサイト。
| |
| − | *[http://www.birds.cornell.edu/ Cornell Lab of Ornithology]
| |
| − | *[http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/completed_essays.html Essays on bird biology]
| |
| − | *[http://www.i-o-c.org/IOComm/index.htm International Ornithological Committee]
| |
| − | *[http://www.mrnussbaum.com/birdsindex.htm North American Birds for Kids]
| |
| − | *[http://www.ornithology.com/ Ornithology]
| |
| − | *[http://elibrary.unm.edu/sora/index.php Sora] — 検索可能なオンラインの研究アーカイブであり、以下の鳥類学学術誌のアーカイブである。 [[w:The Auk]], [[w:Condor (journal)|Condor]], Journal of Field Ornithology, North American Bird Bander, Studies in Avian Biology, Pacific Coast Avifauna, and [[w:the Wilson Bulletin]].
| |
| − | *[http://ibc.lynxeds.com/ The Internet Bird Collection] — 世界の鳥類の無料ビデオライブラリー
| |
| − | *[http://www.birdpop.org/ The Institute for Bird Populations, California]
| |
| − | *[http://media.library.uiuc.edu/cgi/b/bib/bix-idx?c=bix;cc=bix;sid=0c4f6243857204b94fcdebc6dce5d8b2;type=simple;page=browse;inst=bix_10;sort=region list of field guides to birds], International Field Guides database より
| |
| − | *[http://www.rspb.org.uk/wildlife/birdidentifier/ RSPB bird identifier] — 英国のすべての鳥を見分るためのインタラクティブガイド
| |
| − | {{鳥類}}
| |
| − | {{Authority control}}
| |
| | {{DEFAULTSORT:ちようるい}} | | {{DEFAULTSORT:ちようるい}} |
| | [[Category:鳥類|*]] | | [[Category:鳥類|*]] |